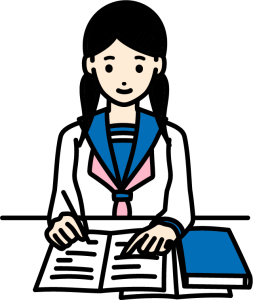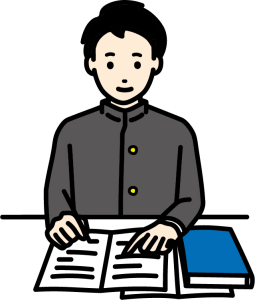合格体験記&親御様メッセージ(2025年 都立立川高校:Sくん)
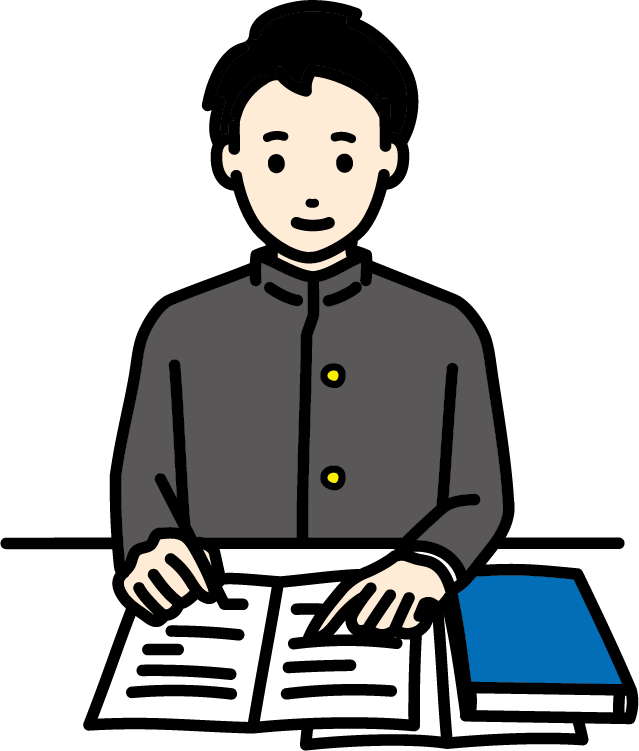
Sくん
入塾のきっかけ
中2の終わりまでは他塾に通塾していました。しかし、中3向けの講座案内を見た時、その塾の指導に疑いの目を持ちました。多い授業と高い費用、周りの塾生のレベルが高くないため、それほど努力をしなくてもトップクラスの順位を安定的に取れてしまう点、先生ごとの授業の質の違いなどが原因でした。
そこで、都立高校に進学したかったこともあり、学志舎の体験に行きました。そこで驚いたのは、圧倒的な塾生の集中力でした。全員が黙って学習に取り組むという理想の環境が学志舎にはありました。また、既に推薦入試で合格した先輩が自立学習に通い続けていることにも感動しました。塾長の過去のデータによる面談もとても熱意がこもっていました。「ここでなら必ず良い結果が得られる!」と思いました。
以上の理由で、中3の始めから学志舎に入塾しました。
変化
集中力です。初めはすぐに集中が途切れていました。解けない問題があるときは、そのようなことが多かったです。
しかし、周りの塾生の集中力や先生方の熱意に感化され、次第に集中力を大きく伸ばすことができました。受験直前では、過去問を3教科連続で解いても最高レベルの集中を保つことができました。5教科連続でも同様です!
勉強以外に学んだこと
コミュニケーション能力です。村岡先生の授業における周囲との意見共有や推薦特訓で伸ばすことができました。
推薦特訓では、面接練習で多くの先輩と関わりコミュニケーション能力が飛躍的に伸びました。そのおかげで、知らない人が多い高校生活への不安も小さくなりました。
印象に残った先生の言葉
塾長の「人と違う結果が欲しいなら、人と違うことをするしかない」です。この言葉を聞いた日から、受験への熱意が高まりました。他の塾生より良い結果が欲しいと思い、学志舎にいる間に加えて家でも自習をするようにしました。また、学志舎の自習室では1秒でも長く勉強するようにしました。
落ち込んだ時の回復法
苦しい時こそ勉強をしていました。合格するために必要なのは結局勉強です。そのため、目標に少しでも近づくために勉強をし続けました。「この苦しい状況を抜け出すには、勉強して偏差値を伸ばすことが一番近道!」と信じていました。
推薦入試で残念な結果になった時も、答案再現をした後、すぐに駅前校で自立学習をしました。それがとてもよかったと思います。そもそも、集中している間は辛いことも忘れることができます。
後輩へ
受験はゴールがはっきり見える持久走です。志望校に合格するために必要な偏差値や内申点は模試がはっきりと示してくれます。推薦入試についても同様です。つまり、何をすればよいのかがはっきり分かります。模試の結果や問題集の正答率などから自分に足りないところを分析し、改善し続けましょう。ありがたいことに学志舎はそのサポートを徹底して行い、必要なプリント、教材を渡してくださいます。質問への対応も素晴らしいです。
このように、学志舎は受験のための最高の環境が整っています。ここに通えているあなたたちはとても「幸せ者」です。それなのに努力しなくて良いのですか?他塾の子より条件の良い持久走なのにだらけるのですか?
「うさぎとかめ」のうさぎは自分の力を過信して、負けてしまいました。学志舎の環境があれば、「受験で合格するための力」が身に付きます。「学志舎に入っていれば受かる」と考えていると、物語中のうさぎのようになってしまいます。しかし、学志舎で努力を続けて「怠けないうさぎ」になれば、他の受験生に大きな差をつけることができます。だからこそ、学志舎でたくさん学んでください。来年の春を笑顔で迎えられるように頑張れ!
親御様
第一志望の立川高校に合格することができ、学志舎の先生方、卒塾生の皆さん、切磋琢磨した塾生の皆さんに心より感謝いたします。
他塾ではなく学志舎を選んだ理由
実は中学入学前に一度、学志舎の体験に行きました。当時は都立志望か私立志望かも決まっておらず、息子も自立学習のピリッと張り詰めた雰囲気が少し怖かったようで、入塾を見送り、他塾に入塾しました。(HPにもありますが、本当にその後の勧誘は一切ありませんでした)
中3になる前に通っていた塾から都立志望か私立志望か、それによってどの学習コースを選択するかという調査がありました。その際に息子と志望校について話し合ったのですが、都立高校に進学したいという思いや、通っている塾に対する思いを聞き、この機会にもう一度学志舎に話を聞きに行ってみようということになりました。
体験に行った日は塾長が対応してくださいました。私は塾長の机の上の綺麗さ、資料の整理整頓の素晴らしさにとても感心しました。それで入塾を決めたというと少し変かもしれませんが、私にとっては「これだけ忙しい中で、こんなにも綺麗にモノを整えられる方が塾長なら安心してお願いできそうだ」と感じました。息子も面談の中で積極的に塾長に質問や相談をしており、その様子を見てその日のうちに入塾を決めました。
受験期における子どもの成長
学志舎に入塾する前から、「勉強しなさい」と言わなくても勉強はするタイプでしたが、今思い返すと「必要最低限の勉強だけ」をしていたのだと思います。もちろん、親が何も言わずとも勉強するのですから良いのですが、学志舎に入塾してからは周りの塾生に刺激を受け、「まだ勉強しているの!?」と親が心配するくらい「納得がいくまで」毎日遅くまで勉強をしていました。そのため、学志舎に入塾してからは息子の勉強に対する満足感が明らかに違いました。
推薦入試では残念な結果となりましたが、悔しい思いをした分、それ以上に成長できたと思います。その日のうちに先生方から励ましの言葉をかけていただき、息子も悔しいながらも踏ん張って乗り越える力を身に付けられました。その力はこの先の息子の長い人生の中でも必ず役に立ち、糧になると思っています。本当にありがとうございました。
見守る親の心境
いくら自立学習に積極的に参加していても、毎日遅くまで勉強している姿を見ていても、やはり受験期が近づくと親としては不安が募ります。そんな私の様子を見た主人から「息子を信じて、いつも通りでいよう」と言われました。できる限り不安な様子は出さないようにしていたつもりでしたが、きっと私の心の中の不安が家中に漂っていたのだと思います。受験に関してほとんど口出ししなかった主人ですが、この言葉に私自身はハッとさせられ「見守る」ことの難しさを感じるとともに、「いつもと変わらない家を保つ」ことに注力しました。
推薦入試の前日、息子が突然、家事をしている私のところに来て「ありがとう」という言葉をかけてくれました。思春期で難しい年ごろの男の子が、わざわざ母親に面と向かって「ありがとう」と言ってくれるなんて、こんなに嬉しいことはありませんでした(合格した時よりも嬉しかったかもしれません)。この言葉をもらったことで、私も右往左往しながらも何とか「見守る」ことができたのかなと感じました。