☆日比谷(合格者)2025年
Iくん ※推薦合格

入塾のきっかけ
私は、中学2年生の6月頃、学志舎に入塾しました。学志舎の卒塾生であり、日比谷高校の卒業生でもある兄から「合うと思うよ」と言われ、興味を持って行った体験授業が入塾のきっかけでした。
体験授業の際に何よりも感じたのは、まるで試験中かのような緊張感・緊迫感でした。最初は圧倒されてしまいましたが、そんな雰囲気の中で一人一人が全力で取り組む姿を見て「ここでなら、自分の限界に挑み自分を高めていける」と思い、体験授業を受けたその日に入塾を決意しました。
自分のミスと向き合う
私は、学志舎に入塾するまで「初めて出てきた問題を解けるように」ということを意識しすぎて、自分のミスと向き合ってきませんでした。そのため、分からない問題があった際には、答えを見て分かったつもりになり、また同じようにつまずくということを繰り返していました。
しかし、学志舎に入塾後は「直し」を徹底的に行うことで「なぜ間違えてしまったのか」「何が足りなかったのか」を分析し、人に説明できるレベルまで理解するようになりました。これによってミスをしにくくなっただけでなく、自分に対する理解度が上がり、問題の取捨選択をうまく行えるようになったため、効率よく確実に点数を取れるようになりました。さらに「直し」によって問題の本質的な部分まで理解することで、様々な問題に応用できる考え方を身につけられ、初見の難しい問題でも解けるようになりました。
今しかできないことだけする
3年生になってからの1年間で村岡先生が何度も仰っていた「今しかできないことだけする」という言葉は、私にとって忘れられない言葉です。
私は受験期を過ごす中で「受験を振り返ったとき、後悔がないようにする」ということを大切にしてきました。後悔をしないような取り組みを行うために何をすれば良いか、はっきりと分かっていなかった私でしたが、この言葉によって「今、自分にできることは何か」ということを常に考え、行動する癖をつけられたと思います。
また、受験期を過ごす中で感じた悔しさや不安をバネにし、成長することができたのもこの言葉のお陰です。私は、模試や過去問でミスをし、自信を失う時期や、不安やプレッシャーに押し潰されそうになる時期を何度か経験しました。しかし、そんなときは「今すべきことは、くよくよ悩むことではなく、努力することではないか」と言い聞かせ「今しかできないこと」に全力で取り組みました。今、受験を振り返って「自分の取り組みに後悔はない」と思えるのは「今しかできないことだけする」という言葉のお陰だと思います。
悔しい時が一番伸びる
もう一つ忘れられない言葉として、布施先生の「悔しい時が一番伸びる」という言葉があります。受験期を通して悔しさや不安に苛まれることが多くありました。そのような時はこの言葉を思い出し「今が一番伸びるんだ」と自分に言い聞かせることで努力できました。不安や悔しさのようなマイナスな感情を原動力にできるこの言葉をこれからも大切にしていきたいです。
「努力」と「自信」が持つ力
学志舎では、礼儀や話を聞く姿勢など、勉強以外にも多くのことを学びましたが、なかでも特に印象に残っているのは「努力」と「自信」が持つ力です。私は元々、学力があまり高くなかったため、日比谷高校に入れる自信は全くありませんでした。また、日比谷高校に受かるために必要な学力と自分の学力との差を実感し、不安に陥ることも多々ありました。
しかし、それらの壁を乗り越えるには努力をするしかないと思い、自分が思いつく限りのことを行いました。その結果「オール5」「模試A判定以上」「過去問で合格者平均を超える」など、自分が目標としていたことを達成することができ「努力」が持つ力を実感しました。
さらに、たくさんの努力をしたからこそ得られた根拠のある「自信」は私を勇気づけてくれました。「自信」とは「頑張ってきた自分を信じる心」です。これを持つことは簡単なことではありませんが「自信」を持てていれば、周りを気にせず、自分の力を出しきれると思います。
「自信」を持って臨めた推薦入試本番では、試験を楽しみ「これで縁がなくても後悔はない」と思えるほど自分の全てを出しきることができました。このような経験から「自信」が持つ力の大きさを改めて実感しました。私がこれらのことを学べたのは、学志舎の独特の緊張感・緊迫感を持った自習室や、私たちを支え育ててくださる先生方、推薦特訓を始めとした楽しい授業といった最高の環境があったからこそだと思います。
推薦特訓
私は、推薦入試直前の2週間で行われる推薦特訓に毎日コースで参加しました。この期間は間違いなく、人生の中で最も自分と向き合い成長した2週間だったと思います。
面接では「自分がどのような人間か」「日比谷高校で何をしたいのか」などを分かりやすく、インパクトを持たせて伝えるために様々な試行錯誤を重ねました。その中で、志望動機や将来の夢を始めとした自分のことについて新たな発見を得られました。集団討論では、話を深めるための着眼点、議論の進め方、意見のまとめ方、話の聞き方などを、様々な人たちと様々なテーマで話し合うことを通して身につけられました。小論文では、とにかく量をこなし慣れていくことで、文をコンパクトにわかりやすく書く力、資料から作問者の意図を掴む力を身につけられました。
このように「話す」「聞く」「書く」「読む」という一生使える四技能を高められた本当に貴重な経験でした。また、この2週間では、誰にも負けないと思えるほどの圧倒的な量の練習をすることができたため、推薦入試本番では「自信」を持ち、自分の全てを出しきれたと思います。
後輩の皆さんへ
受験当日に「志望校への思い」と「自信」を持っていれば、たとえ周りの人が優秀な人ばかりでも合格できると私は思います。そのために、「今自分にできること」を考え、皆さんが思いつく限りのことを全力で行って下さい。
学志舎には、良い雰囲気の自習室、高め合える仲間、支えてくれる素晴らしい先生方など、その努力をするための環境が整っています。入試本番、自信を持てるように一日一日全力で頑張って下さい。応援しています。これからは、学志舎で学んだことを皆さんに還元し、全力でサポートしていきたいと思っているので、今後ともどうぞよろしくお願いします。
Kさん
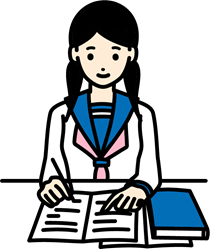
入塾後の変化
私は小6の秋から学志舎に通い始めました。それまでは勉強に馴染みがありませんでした。しかし、学志舎の緊張感と刺激に満ちた環境に影響され、勉強が好きになりました。
落ち込んだ時に響いた言葉
過去問の国語で平均点に大きく届かないことがありました。その解答用紙を先生に提出し、返ってきた紙には「上手くいかなかった回の見直しが次に活きる!!」と書かれていました。しょんぼりしていた心が回復し、やる気が漲りました。
模試結果との向き合い方
私は10月から12月まで、自校模試の数学の偏差値が60前半を彷徨っていました。思うように伸びない成績に、途方に暮れたのを覚えています。しかし、学志舎の数学オリジナルプリントを活用し、幾度も問題を解き直したことで、初冬ごろから過去問の点数が格段に上がりました。
そして、1月の模試で、数学の偏差値は67へとupしました。この経験からわかるのは、努力が結果として表れるには、一定の時間が必要だということです。言い換えれば、すぐに結果が出なくても、学志舎で勉強を継続することで、そのうちに結果が出ます。
日比谷高校の入試
日比谷高校の英語は、他の都立高と比べ記述問題が多いです。
そこで、次のことを繰り返しました。
「まず自力で書いてみる」
「先生に添削して頂く」
「それを踏まえて再び書く」
添削は、先生が改善点を伝えつつたくさん褒めてくださり、モチベーションが上がりました。このような記述対策のおかげで、英語の実力を盤石なものにできました。
先生方や卒塾生の存在
塾長はガッツの塊です。
生徒の力を最大限に伸ばす、独自の数学の解説は今後も忘れられないと思います。解説で頻出の合言葉を頭の中で唱えながら問題を解いていました。
塾長は、時には塾生のやる気を出すアツい言葉を、時には心を和ませる塾長の次女さんの珍回答を教えてくださりました。塾長の言葉に助けられ、メリハリをつけて受験勉強に取り組むことができました。
村岡先生のお話は塾生の世界を広げてくれます。中でも「◆◆という概念を持たない民族の話」と「●●現象の話」は、私の興味のある分野だったので、ワクワクしながら聞いていました。
推薦入試で不合格だった際は、「日比谷高校に腹を立てている」「一般入試は心配してない」と仰ってくださいました。私は推薦特訓に全力を注いだ分、不合格という事実にかなり落ち込んでいました。しかし、この言葉をいただき、気持ちが切り替わりました。必ずリベンジしてやるぞ、と闘志が燃えたのを覚えています。
推薦特訓中、I先輩に、日比谷高校の生活について伺う機会がありました。実際に志望校である日比谷高校の卒業生と話したことで、高校への憧れが増し、頑張る力となりました。
一般入試の直前には、M先輩と面談をしました。当日焦らない方法等を教わり、安心して入試に臨むことができました。
この受験期を振り返り、素晴らしい先生方、数多くの先輩、そして隣で勉強した同級生の助けをいただきました。心から感謝しています。このような心強い存在の多さも、学志舎の魅力です。
後輩へ
良い結果が出ず落ち込んだときこそ、学志舎に行って勉強してみてください。悔しい気持ちをバネに集中した時間を過ごせば、合格が待っています。焦らずに、日々全力を尽くしてほしいです。
今後は、後輩の皆さんを応援しに学志舎に参りたいと思います!
