☆西(合格者)2025年
Yさん ※推薦合格

入塾のきっかけ
私は中学2年生の冬期講習から学志舎に入塾しました。以前通っていた大手塾では、進度の早い授業にモチベーションを保つことができませんでした。高校受験が近づき、このままでは第一志望の西高校は到底無理だということで、転塾を決めました。塾長との面談で、「君なら西を目指せるよ。」という言葉をかけていただき、この塾で第一志望に向けて頑張りたいと思い、入塾を即決しました。
入塾前と入塾後の変化
テスト期間も授業が続いていた大手塾では、テスト勉強も家での勉強も中途半端になってしまい、内申は低迷していました。受験(特に推薦入試)に内申が重要だということも知らなかったからです。また、自分から勉強をするという意欲も全くありませんでした。
しかし、学志舎にはまずテスト準備期間があります。高い目標に向かって集中して取り組むことができ、最終的に内申を44まで上げることができました。さらに、共に頑張る仲間の姿が常にあるので、もっと勉強したいという意欲が自然と湧くようになりました。3年の秋、5時間集中し続けることができ自分でもとても驚きました。
推薦入試
私は、最後の模試の成績が全く西を受けるレベルに届いていなかったため、ここで合格が叶わなければ志望校を変更するという覚悟を決め、背水の陣の状況で推薦特訓に申し込みました。不安でいっぱいでしたが、学志舎名物の推薦特訓は話に聞いていた以上に充実した時間でした。
先輩方との面接練習では、自分の課題を客観的な視点でアドバイスしていただけるので、練習を重ねるたびに大きな成長を感じることができました。また、西高校の先輩には学校生活についてなど面接以外のお話も聞くことができ、より合格への思いを強めて本番に臨むことができました。
さらに、合格という同じ目標に向けて努力してきた仲間とメッセージを交換したり、課題を見つけあったりすることで、学志舎全体がチームとなって立ち向かっているのだということを実感する時間でもありました。
忘れられない言葉
2つあります。
1つ目は、村岡先生の「量が質に転化する」という言葉です。私はこの言葉を胸に、苦手だった数学の学志舎オリジナルプリントをボロボロになるまで何周もしました。量を重ねていくことで、解くコツを自然と掴むことができ、今までなかったような問題にも対応できるようになります。
2つ目は、塾長の「チャレンジャーにはチャレンジャーにふさわしい努力を」という言葉です。私は前述した通り、西を受けるには程遠い偏差値でした。そのため、志望校を変えずに挑むというのはかなりのチャレンジだったと思います。しかし、誰よりも多くプリントや過去問を周回したり、推薦期間においても作文を1日に何年分も書いたりして、自分にできうる限りの努力をすることを心がけました。
後輩へアドバイス
学志舎は、他塾よりも圧倒的なエネルギーに満ちた塾です。心強いアドバイスや質の高い授業を提供してくださる熱い先生方、不安な気持ちに寄り添ってくださる先輩方、そして志望校は違えど共に「合格」に向けて努力する仲間がいます。
ここまで縦のつながりも横のつながりも強い塾はどこにもありません。まず、学志舎の塾生として努力できているということに誇りと自信を持ってほしいです。そして、「私は絶対にここの高校の〇〇期生になるんだ!」という強い思いを持ってください。当日の力になってくれるのは、先生や先輩、同期、応援してくれる家族の存在ももちろんですが、自分の「合格への執念」が爆発的なエネルギーになります。最後まで絶対に諦めず、最高の環境で合格を掴み取ってください。応援しています!
Hくん ※推薦合格

入塾
第一に、他塾とは一線を画す「空気」と個性豊かな先生に私は魅せられました。学志舎を見つけて無料体験に私を誘ったのは親であり、そこで出会ったのが塾長でした。私は中学受験のため某大手塾に通っていましたが、その時の先生とは明らかに雰囲気が違いました。塾講師としては異例の経歴もさることながら、実際にお会いしてみるとその雰囲気に圧倒されました。ただの「教えるプロ」ではなく「人間のプロ」なのだと小学生なりに感じ、私は学志舎の個性的な先生のもとで学んでみたいと強く思いました。もちろん、塾長だけでなく学志舎の先生方は全員強い個性のある「人間のプロ」です!
第二に、良質な「環境」に魅力を感じたことが挙げられます。以前の塾では授業中でも常に会話が絶えず落ち着きがなかったですが、学志舎では休み時間でさえ時間を惜しみ黙々と課題に取り組む様子がとても印象的でした。当時の私はあまり自ら進んで行う勉強―すなわち「自立学習」―ができない類の少年でしたが、学志舎の良質な環境の輪に入れば私も極めて高い集中力が得られるのではないかと感じました(※これが私の学志舎に入塾する動機になります。ただし、確かに環境も人を変える大きな要因になりますが、最後に自分を変えるのは自分自身に他ならないことは心にとどめておいてほしいです。)
「学志舎マジック」によるBefore and After
入塾後に私に生まれた変化は、「自分から進んで学習に臨む力を得たこと」でした。以前の塾にも自習室はありましたが、私は授業が終わればすぐに帰る生粋の「定時帰宅生」でした。学志舎に入塾後も変わらず定時帰宅生であり、残念なことに家で勉強する姿勢は皆無で寝るだけでした。塾にいる間に勉強すれば、学力をさらに向上させることができます。自分がのんきに寝ている間、授業終了後に教室に残り学志舎の塾生が学力を上昇させていることに私はやっと気づき、さらに感じたのが「危機感」でした。私が軽く構えているのに対し、学志舎の塾生は決死の覚悟で勉強に挑んでいました。このままでは置いていかれると焦り自習室を利用するようになりました。次第に最終時間まで残って勉強できるようになり、3年生になってからはほとんど毎日塾に通っていました。
次なる変化は学校の成績です。学志舎では定期考査後に公開される成績表を必ず先生と共有し以降の勉強の方針を立てます。先生が指し示してくださる方針を信じ、その方針を具体的にどのような行動に落とし込むか考え、それを実行する。そうすると自ずと全体的に学力のバランスが取れて成績が上昇しました。それほどまでに先生方の目と狙いは鋭いのです。
勉強以外に教わったこと
学志舎に通塾することで、人間として生きていく上で必要な思考力の成長がありました。例えば、塾長から「おごってもらったときにする三段階のお礼」についてのお話があり、このお話をただ「おごってもらった時のために覚えておこう」だけで終わらせるのはもったいないです。さらに発展させて「人から何かしてもらった時」全般に使えます。このように、先生方は生きていく上で活かせるチャンスがいくらでもある貴重な情報を与えてくれていたのです。その情報を使っていかに自分の人生を豊かにするかは自分次第あり、自分で考えて教えていただいた以上のことをできるようになったのは他でもない学志舎のおかげです。
また学生としてだけではなく人間的にも成長できました。何と言っても先生方は「人間のプロ」なのだから! 普段の授業中だけでなく、教室のある建物に入るときから学志舎は礼儀であふれています。挨拶は欠かさず、応答ははっきりと、聞くときは目を見て頷く、すべてが社会に出てからも人間として必要な姿勢だと思います。授業の合間に先生方が話してくださる教養や経験、生きるコツも貴重なアドバイスでした。私が学志舎に入塾してどれほど「すてき人間」になれたかは計り知れません。このようなアドバイスを活用しながら学校での態度改善はもちろん社会に通用する人間に成長できたと思います。
忘れられない経験:推薦特訓
学志舎で経験し学んだことはあまりにも多すぎてここにはとても書ききれませんが、私の人生の転換期となった推薦特訓は特に忘れられない経験です。
私の素内申点は過去の推薦入試合格目安に達していなかったにもかかわらず、ありがたいことに先生方は私に推薦特訓を受けさせて下さいました。まず推薦特訓で驚いたことが会話の多さです。今までほとんど言葉を交わしたことがない同期達と面接や集団討論などを通してたくさん会話しました。みんなフレンドリーで、中にはその日初めて知り合ったにもかかわらず休み時間に気軽に声をかけてくれた友人もおり、「居心地の良さ」を強く感じました。推薦特訓に参加して自分でも驚くほどの全力を出せるようになり、たくさん作文を書き、面接練習をしても疲れるどころか何度でもトライしたい、心の底から「楽しい」と感じ、土日コースだった私は週末が待ち遠しく思っていました。作文をたくさん書いて先生の添削を待つ時も、産業プラザと第2教室を全速力で往復する時も、当日試験がいよいよ始まるその時も全身全霊ですべてに立ち向かうことができました。
さて、そんな私の人生の盛り上がりを支えてくれたのは同期達や先生方…だけではありません! 学志舎の強みの一つ「卒塾生」つまり先輩方の存在です。私はほとんど中学校で先輩と関わる機会がなく今回の推薦特訓で「年の近い目上の人」とお話しできたことはとても新鮮でした。面接練習では私の欠点を的確に見抜き、それと同じくらい長所も拾って下さったおかげで自分をよく客観視でき、先輩の励ましに力強い安心感も得られました。さらに先輩方は練習の合間に私の志望校の詳しい様子なども教えてくださりそれも強いモチベーションになったと思います。
私は内申点のビハインドに弱気になっていた時もありましたが、推薦特訓を受けながら熱くサポートして下さる先生方、親身になって寄り添ってくださる先輩方、本気で取り組み合格を目指しながら共に素敵な時間を分かち合った同期達など多くの人に囲まれて、「同期達と春に志望校で会いたい」、「先生方と先輩方の思いを一つも無駄にしたくない」と感じ、推薦入試に強い心で立ち向かう覚悟を決めました。もし私が学志舎に入塾していなかったら、このような充実した日々は一日も過ごせず中途半端にあきらめる覚悟の足りない人間のままだったでしょう。改めて、私の「人生」を造ってくださった先生方、先輩方、同期達に感謝したいと思います。本当にありがとうございました。
後輩へ
第一に、自分を信じ決してあきらめないでください。「自分には向いてないから」、「どうせできないから」、そのような理由で逃げることはやめましょう。正直に白状すると、私はずっと逃げてきました。それで結果的に良い方向に向かったことは一つもありません。一瞬のその場しのぎで残るのは一生の後悔。私は推薦特訓で初めて逃げるのをやめて踏みとどまりました。もしあそこで逃げ続けていたら私はこの体験記を書くことはなかったでしょう。逆に言えば、逃げずに立ち向かえば、必ず何か得られます。望んだ結果でなくとも悔いなくすがすがしく終えられるはずです。
第二に、立ち向かったら自分の方から前進しましょう。学志舎は最高の経験と空間を与えてくれます。しかし、それをどう利用するかは自分次第です。ずっと受け身になって与えてもらい次を待つのではなく、自分から求めて行くのです。自分から得ようと思えばいくらでも得られます。ただ、一人でそれをしなければいけないわけではありません。学志舎の先生方、先輩方、同期達。両親、学校の先生方、友人、みんなに助けを求めても全然いいのです。大事なのは自分から求めに行くこと、自分でその環境を最大限活用すること。学志舎はただの学生を育てる場ではありません。人間を育てる場です。あなたがなりたい人間になるための材料は探せばいくらでも見つかります。いつか学志舎でなりたい自分になろうとしているあなたとお会いできたらうれしいです。
Aさん ※推薦合格
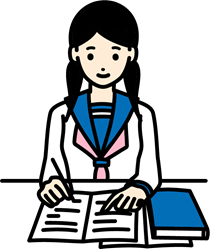
入塾のきっかけ
塾を見学した際、全員が集中して勉強に取り組んでいる姿に驚きました。ちょうど推薦特訓が行われており、大勢の先輩方と塾生が面接練習をしている熱気に圧倒されました。その様子を見て、「自分もこの推薦特訓を受けたい!」と強く思い、学志舎に入ることに決めました。
変化
学志舎に入塾してから、私は二つ変化を実感しました。
一つ目は、問題を速く解く力がついたことです。入塾したばかりの頃は、他の塾生の問題を解くスピードに圧倒されるばかりでした。しかし、私も「とにかく手を早く動かす」ことを意識し、少しずつ解くスピードが上がっていきました。
二つ目は、苦手だった数学の得点が伸びたことです。今までは難しい問題の解説を読んでも、解き方がまったくわからないことが多くありました。しかし、学志舎オリジナルプリントのおかげで、解法パターンをしっかりと頭に入れることができました。何度も繰り返し取り組み、模試の点数も徐々に上がっていきました。
先生の言葉
中学3年生になると、学校全体が受験ムードになっていきました。私は部活で、勉強時間が削れてしまうことも多くあったため「勉強している他の受験生と差がついてしまうのでは…」と不安になることもありました。そんなとき、塾長が「部活は悔いのないようにやりきった方がいい」と言ってくださり、その言葉に背中を押されました。
そのおかげで、最後まで全力で部活に取り組み、清々しい気持ちで引退することができました。引退後はすぐに気持ちを切り替え、受験勉強に集中することができました。
また、夏期講習のときには気が緩んでしまうこともありましたが、先生の「明日が本番でも大丈夫なように」という言葉にハッとさせられ、気を引き締めて勉強に臨むようになりました。
落ち込んだとき
1月最後の模試でまさかのC判定を取ってしまい、絶望のどん底にいるような気持ちになりました。しかし、ずっと目指してきた第一志望校・西高校を諦めることができず、一般入試で挑戦することを決意しました。
塾長に相談した際、過去の先輩方のデータを示しながら具体的にアドバイスをくださったおかげで、冷静に志望校を決めることができました。私は楽観的な性格なため、休憩時間にはあえてC判定の模試結果を見返し、「このままではダメだ」という危機感を持って勉強に取り組むようにしました。
推薦特訓
模試でC判定を取ってしまったことで、推薦特訓をこのまま続けていいのかと悩むこともありました。しかし、村岡先生の「Aさんは推薦で受かる」という言葉に励まされ、迷いなく推薦特訓に参加し続けました。
私は火・土・日曜日の推薦特訓コースに参加し、特訓がない日には作文を何枚も書きました。先生方が丁寧に添削し、すぐに返してくださったおかげで、自分の文章の問題点をすぐに直すことができました。何度も書くうちに、作文力が向上しているのを実感し、自信につながりました。
推薦入試本番では緊張しましたが、先生や塾生、先輩方からもらったメッセージを見て元気をもらいました。また、先生方に褒められた作文を見返すことで、「自分なら大丈夫」と落ち着くことができました。さらに、塾で日頃から「こんにちは!」「ありがとうございました!」としっかり挨拶する習慣をつけていたおかげで、面接の最初の挨拶は自然にでき、その後の受け答えも落ち着いて臨むことができました。
後輩へ
まだ時間があると思っていても、最初のうちは気が緩んでしまいがちです。しかし、受験までの一年は思っている以上にあっという間に過ぎてしまいます。今のうちに危機感を持ち、勉強に取り組むことが合格の道につながると思います。
今後、志望校と自分の実力が合わずに、進路を変更するか悩む人もいるかもしれません。そんなときに大切なのは、「自分で決めること」です。たくさん悩んで、自分が少しでも納得できる道を選びその道を突き進んでください!
英語の長文の音読や授業の復習など、できることはすべてやり、自分の自信につなげてください。最後まで諦めずに頑張ってください。応援しています!!
最後に
布施塾長、村岡先生、佐藤先生、埴村先生、山田先生、先輩方、本当にありがとうございました!!
Sくん ※推薦合格

入塾のきっかけ
小6の3月頃に、母が連れて行ってくれた塾が学志舎でした。当時私は、都立中入試にて不合格となり、落ち込んでいました。しかし、入塾テスト後に塾長と村岡先生から「高校受験でリベンジだ!」と言われ、気持ちが軽くなったことを覚えています。
また、私は中学3年生の夏までは、部活も含めて学校生活を充実させたいと考えていました。その中で通塾となると、学校生活の妨げや負担にならないか不安でした。しかし、「週2回の授業」というカリキュラムを聞き、非常に驚くと同時に、学志舎なら中学とも両立できるかもしれないと感じたことを覚えています。
入塾前と入塾後の変化
元々集中力や学力には自信がありましたが、「演習量」が不足していました。また、集中力を今のように何時間も持たせることはできませんでした。
入塾してからは、学志舎はこれ以上ない最適な学習環境だと気づきました。周りから聞こえるのはひたすらペンを動かし続ける音だけ、という非常に静かで落ち着いた環境のおかげで、「高い集中力」を身につけることができました。
また、学志舎には一心不乱に問題を解き続ける、ある種異様な光景があります。このお陰で、疲れた時でも「負けていられるか!」と対抗心を燃やし、問題に向き合い続けることができました。
また、中1の1学期の素内申は38でしたが、中3では1学期からオール5の評価を頂くことができました。これは、学志舎がテスト期間は授業をストップし、自習時間に充ててくださったからだと感じています。他にも、先輩方や先生方から教わる内申up法を実践したこともオール5に繋がった要因だと思います。特に、中3の1学期からオール5を掴み取れたことは、精神的に大きな支えとなりました。
落ち込んだ時とその回復法
夏期講習ごろ、私は数学の授業が苦痛でした。関数や図形問題で、どこから手をつければ解くことができるのかわからない私と対照的に、周囲から聞こえる「終わりました」はとても悔しく、焦りを覚えました。
しかし、塾長に相談した際、「今は解けなくて当たり前や。入試問題を今解けないのは周りも同じや。」と言われました。それ以来、ひたすら手を動かし続け、何度も反復して解いていくうちに、不思議と解くことができるようになっていました。
悩む暇があれば手を動かすこと、これが私の中で一番良い解決策だと思います。この解決策は、後の推薦特訓でも活かすことができました。
推薦特訓
作文を少しでも多く書き、頭の中では常に面接のことを考え、疑問があればすぐ先生方や先輩方に質問するようにしていました。1日に作文を9つ書いた日もあり、膨大な演習量を解く中で、自分が短期間に急成長を遂げていることを強く感じたあの感覚は、今までで初めてでした。
他塾ではあり得ない、志望校に合格した卒塾生の先輩方が、私たちを全力でバックアップしてくださる環境は本当にありがたかったです。実際に聞かれた質問を使って面接練習をしたりと、本番を見据えた効果的な練習ができました。
不安になることもありましたが、「悩む暇があれば動け」を常に掲げて行動していました。その結果、自分の能力や内容をよりハイレベルなものに突き詰めることができ、「合格しか見えない」というメンタルに持っていくことができました。
忘れられない言葉
塾長が何度も仰っていた「人と違う結果が欲しいなら、人と違うことをするしかない」という言葉です。中3の1学期からオール5を掴み取れたのは、これを実践したからです。
私は委員会や係活動を「先生と交流する場」と捉えるようにしていました。学級委員を務めることで、先生方とのコミュニケーションをとると同時に、クラスをまとめる存在として先生方から信頼を勝ち取ることができたと思っています。係活動では、成績を上げたい教科の係につくことで、担当の先生と会話する機会を作り出し、同じように信頼を勝ち取りました。これによって授業や提出物以外のところで自己を高めることができました。
勉強以外に教わったこと
「コミュニケーション能力」です。中3初期に村岡先生がしてくださった「コミュニケーション講座」では、「話す」と「聞く」の両方を高めることができたと思います。「相手の目を見る、頷く、相槌を打つ、笑顔」どれも当たり前のことですが、改めて重要性に気づくことができました。この経験もやはり、オール5、そして推薦特訓に生きてきた経験です。
後輩に一言アドバイス
「使えるものは全て使う」この姿勢を持って過ごしてほしいです。例えば、先ほども挙げたように委員会や係活動です。ほかにも先輩にも助けを求めることもありだと思います。内申を取るためにどんなことに取り組んでいたのか聞いたり、高校について質問したりなど、色々なところでアドバイスを受けることは、自分の成長にとても効果的です。仲のいい先輩に相談してみてください。
Nさん ※推薦合格
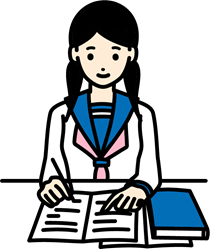
入塾のきっかけ
小さい頃から西高生の兄の影響で西高に憧れており、また推薦入試を受けてみたいと思っていました。そのため、西高への合格者数が多く推薦入試に強い学志舎に入ろうと決めました。
入塾前と入塾後の変化
私は中3の7月に学志舎に入塾しました。それまでは長時間勉強が本当に苦手で、1日2時間できれば良い方でした。入塾してもなかなかすぐには変わらなかったのですが、夏期講習で毎日9〜10時間勉強したことを通して、かなり長時間集中することに慣れたと思います。全員が集中して取り組む環境に最初は気圧されていましたが、気づけば自分もその一部になっていました。愚直に机に向かう経験は学志舎でないとできなかったと感じています。
また、学志舎では徹底的に歴史の年号を覚えたり、理科の暗記の方法を教えてもらったりと理社の対策を十分に行うことができました。他の塾に通う友人の様子を見ると、ここまで理社に力を入れているのは学志舎の特徴の一つだと思います。このおかげで社会は安定して偏差値70以上を、また理科は直前の模試で満点を取ることができました。
推薦特訓
推薦特訓は本当に楽しかったです。作文、面接、集団討論、どれも間違いなく1日目とは比べものにならないくらいに力をつけることができました。特に集団討論は学志舎で練習できて良かったと心から思っています。私は当日に司会をしようと思っていたのですが、練習する中で自分には向いていないのではないかと不安に思うことがありました。しかし、先生が熱心に見てくださり、的確なアドバイスも頂いてとても自分の力になりました。
本番の推薦入試では、例年と傾向が変わっていて一瞬焦りましたが、すぐに学志舎で何度も練習してきた進め方が使えると気づき、いつも通りの司会ができました。これは一般入試でも言えることですが、学志舎で西高だけでなく他校の過去問にも取り組んだことで、どんなスタイルの問題にも対応できるようになったと思います。
忘れられない言葉
推薦特訓の際に村岡先生がおっしゃっていた「遠慮は時間の無駄」という言葉が心に残っています。この言葉を受けて、わからないことを質問するようになり、自分の成長につながりました。
勉強以外に教わったこと
笑顔でいることの大切さを学びました。推薦特訓で先生や先輩から「笑顔が大事」と教わって、推薦練習のときはもちろん日頃からたくさん笑うようにしました。本番の集団討論が終わった後、同じグループだった人から「笑顔でうなずいてくれて話しやすかった」と言われた時は、学志舎で学んだことが生きたと感じられ、嬉しかったです。
後輩へ
勉強でわからないことはもちろん、勉強方法など不安なことは何でも先生に聞くべきです。学志舎の先生方は私たち生徒のことを一人一人よく見て考えてくださっています。「遠慮は時間の無駄」、質問はどんどんして、アドバイスを吸収して成長してください。
最後に
内申が43と推薦入試を受けるにはあまり高くなかったので、最初は受かったらラッキーだと思っている程度でした。しかし、同じように西高を目指す同期と(もちろん西高志望でない人とも)切磋琢磨し、先輩や先生方から熱い言葉をもらう中で、入学への思いがどんどん強くなって、合格以外見えなくなりました。高い志をもってひたむきに取り組む仲間がいたから、最後まで頑張ることができました。
推薦特訓の最終日、同期と「絶対受かろう!」と声を掛け合ったことも、同期が私の合格を自分のことのように喜んでくれたことも、ずっと忘れません。「一生忘れられない出会い」をありがとうございました。
Iくん ※推薦合格

入塾前と入塾後の変化
学志舎に入塾する前は某大手塾に通っていたものの、ハードな授業カリキュラムについていけず、学習意欲が低いままでした。また勉強に対する目標も設定しないままで、まさに先が見えない状態でした。
しかし、入塾後は熱い授業をしてくださる先生方、志望校や目標を持って一生懸命勉強する同級生たちと出会ったことで、自分の目標を見つけ、学習意欲を高めることができました。
推薦特訓
推薦特訓は、面接、集団討論などをきちんと練習してきておらず、自信がない中でスタートしました。しかし、村岡先生からの「今しかできないことだけやる」という言葉は私を奮い立たせてくれ、推薦特訓でしかできないことに対し、自分から逃げずに向き合うことができました。
例えば、作文では最高で 1 日に 12枚書き、面接なども声が枯れるほどに取り組みました。この努力が推薦合格につながったと考えています。
内申up
中学校の授業ではどんなことでも先生の話していたことはしっかりとノートに書き、振り返りのプリントなどは◆◆するなどして提出物の内容を充実させました。
また、学志舎では定期テスト2 週間前には通常授業がストップするため、その期間は学校の勉強に専念できます。この学志舎の環境のおかげで、中学3年の 2学期にはオール 5をいただくことができました。
後輩のみなさんへ
上記の村岡先生の言葉通り、「今しかできないことだけ全力でやる」ことが大切です。受験生にとって、休憩中にスマホを見ることはいつでもできますが、自分の人生や志望校について考え、自分と全力で向き合っていくことはその時しかできません。私は自らと全力で向き合い、逃げなかったからこそ西高の推薦合格をつかみ取ることができました。
また、全力で向き合うためには、先生を信頼することが不可欠です。学志舎の中で、先生を信じた上で自分と一生懸命向き合うという「今しかできないこと」を全力で行い、自分たちの志望校の合格を勝ち取ってください!応援しています。
Bさん ※推薦合格

入塾のきっかけ
中学3年生の夏期講習から入塾しました。私はそれまで家で勉強してきました。しかし、当時は部活で忙しかったため、どうしても勉強できる時間が限られており、演習量が不足していました。
見学で学志舎を訪れた際、生徒の方々が黙々と自習されている姿を見て、「ここなら自分の課題である演習量を解決できるだろう」と考え、入塾しました。
入塾前と入塾後の変化
入塾前は苦手としていた数学と国語でしたが、学志舎で過去問を沢山やり続け、演習量を確保できたことで、勉強のリズムを掴むことができ、模試の偏差値も伸ばすことができました。
また、集中力や積極性も身につけることができました。家で勉強していた際、上手くいかなくて途中で投げ出したりすることがよくありました。しかし、学志舎の自立学習では、途中で辞めたくなっても、両隣で同級生が頑張っている様子を見て「自分もここで諦めてはいられない」と思えるので、毎日やりきることができました。その結果、家でも塾の様子を思い出し、長時間集中して勉強できるようになりました。同級生と切磋琢磨できる学志舎だからこそ経験できたことだと思います。
私は入塾前、人に質問しに行ったり、添削を受けたりすることに苦手意識がありました。しかし、塾長の「他人と違う結果が欲しいのなら、他人と違うことをするしかない!」という言葉が、能動的に動く姿勢の大切さに気づかせてくれました。自分の殻を打ち破り、先生方に添削などを積極的にお願いすることができるようになり、その結果、成績も安定しました。塾長をはじめとした先生方の熱い言葉と、質問や添削を快く引き受けてくださる先生方の手厚いサポートが私を成長へと導いてくれました。
推薦特訓
2週間の推薦特訓は特に印象に残っています。
集団討論の練習では、先輩や先生方から毎日貴重なフィードバックを頂きました。それを吸収しながら練習を重ねるうちに、データを読み取る際の解像度が上がっていくのを実感しました。この経験は推薦入試に限らず、将来の仕事にも大いに役立つと感じています。
また、他の塾生と交流する中で、自分の視野を広げることもできました。面接練習では、志望校の先輩に直接見ていただくことで、志望校への憧れを強くすることができました。
推薦特訓は同級生や先輩、先生など多くの人との関わりにより、自分を成長させてくれる素晴らしい機会です。ここでの経験を、今後の人生に生かしていきたいと思います。
後輩のみなさんへ
学志舎には、思う存分努力できる環境が整っています。それを最大限活用し、毎日悔いのないようにやりきることで、きっと志望校に合格できると思います。応援しています。
Nくん ※推薦合格

入塾のきっかけ
小学生のとき、都立中受験をするために他大手塾に通っていました。しかし、塾の方針に自分が合っていないと感じることが多々あり勉強のパフォーマンスがよくありませんでした。
都立中が不合格と分かった日から、高校受験でのリベンジに向けて「自分の学力を最大限高められる塾」を家族で探しました。その時に、姉の友人が通っていた塾として「学志舎」が候補に挙がりました。「勉強が苦手な人でも勉強に集中して取り組める塾」と聞いて、体験に行きました。
初めて学志舎の教室に入ったときに、全員が喋らず、黙々と学習に取り組む姿に大きな衝撃を受けた記憶があります。「ここなら私でも集中して学習に取り組めるのでは…?」と思い、入塾を決めました。
入塾前と入塾後の変化
「人の話を聞く姿勢」が身に付きました。学志舎では当たり前のことになっている「背筋をのばす」「相槌を打つ」「目を合わせる」という行動は人の話を聞く上で非常に大切だと思います。
また、集中力が格段に上がりました。入塾したての頃は学習を1日30分できるかどうかすら怪しいレベルでした。しかし中3の夏期講習では授業終わりの15時から自習終了時間の19時まではもちろん、長い日は20時過ぎまで自習したことがありました。勉強が苦手な自分をここまで集中させられる学志舎の自習環境は本当に凄まじいです。
学志舎での授業
布施塾長の授業では、実際の試験の時に役立つアドバイスやこれから生きていく上で役立つ考え方を毎回学ぶことができ、前向きになれました。解説はスピーディーなのにとてもわかりやすく、1回の授業で非常に多くの学びを得ました。また、塾長の「人と違う結果が欲しいなら、人と違うことをするしかない」という言葉は自校作成校を受験する上では非常に大切だと思います。この言葉のおかげで努力することができたといっても過言ではありません。
村岡先生の授業では、社会や国語のおもしろい豆知識をはさみつつ、論理的な解説がされていてわかりやすかったです。自己PRカードの添削や推薦特訓では自分の性格や特技、将来の夢などについて深く考え「これからどう生きるか」を考える機会になりました。コミュニケーション講座では、相槌の効果など「コミュニケーションの上で重要なこと」つまり「これからの人生で必要な力」について学ぶことができました。
そして中1、中2のときにお世話になった先生方の授業でも細かくわかりやすい解説がある上に、「おもしろかった最近の話」「理科分野の豆知識」「高校受験の時の苦労」など、ためになりかつ面白い雑談があり、非常に質が高かったです。
勉強はもちろん、人生観や豆知識も学べる学志舎の授業は唯一無二だと思います。学志舎の授業で得たことを今後の人生で活かしていきたいです。
後輩へのアドバイス
私の場合、体調が悪くなる日が多く、学志舎に行けない日もありました。そのため「元気な日は必ず学志舎に行くようにする」「行けなかった日は英単語や歴史の年号などの暗記をする」というように、できるときに最大限努力することが大切だと思います。
Yさん ※推薦合格

入塾のきっかけ
「学志舎に入りたいな…」と思ったのは推薦特訓や合格体験記の記事を読んだ母親にその魅力を聞いたからでした。
私が学志舎に入ったのは中2の7月です。高い合格率を誇るレベルの高い塾と聞いていたため、私がきちんとついていけるかどうか母は心配していました。しかし、私は「ここなら絶対大丈夫だ!」と思いました。ついていけなかったらどうしようといった不安や、本当に大丈夫なのかと疑う気持ちなど、そのようなものは何も感じなかったのです。「絶対大丈夫だ、ここは今までの塾と違う」と直感的に思ったのが決め手でした。
入塾後の変化
入塾前は集中力も散漫、だらだら勉強している酷い状態が多かったのですが、入塾後は勉強の成果がきちんと出てくるようになりました。やはり自立学習で「意味のある勉強」ができるようになったことが一番の要因だと思います。
落ち込んだ時とその回復法
まず一つは、模試で一度「C判定」をとったことです。推薦特訓のコースが決まる直前の模試だったので、「毎日コース」希望だった私にとって死活問題になりました。思春期ゆえに親の前では平静を装っていましたが、内心はとても凹んでいました。
西への愛校心が足りていない自分の不甲斐なさへの憤りと、しんみり自己反省会をしている時にズカズカ怒ってきたお母さんへの憤りが濁流の如く溢れ出たのを覚えています。その濁流に乗ったように猛勉強し、次の模試では「A判定」を取ることができました。勉強内容は主に今までの模試の直し、苦手教科の数学については学志舎のオリジナルプリントが中心です。
私はこのような場面での「火事場の馬鹿力」を大切にしました。むろん、計画的にできるに越したことはないですが、もしうまくいかなかった場合、必ず焦る気持ちが出てくるはずなんです。その気持ちをそのまま勉強にぶつけてください。これは、志望校を愛していればきっと湧き起こるはずの最強の原動力。「ピンチはチャンス理論」はきちんと成り立つんです。学志舎生ならうまく濁流を操れると思います。だから凹んでも、そのまましおれるのではなく「やり返してやる、受かってやる」と好戦的にいきましょう。
もう一つは、内申が思うように取れなかったことです。私は学年屈指の体の硬さで保健体育は見事「4」を叩き出し(ぎりぎりテストでカバー)素内申44で挑むことになりました。西の推薦入試となると学志舎以外にもオール5の人がたくさんいるはずです。360点に換算してみたら思ったよりオール5と差が開いていたのを知り、頭の中で、ヴェルディの「怒りの日」が流れたのを覚えています。
しかし、メンタル欠損は試験において最大の敵なので、私はなんとか健やかに入試を迎えられるようにと熟考の末、こう考えました。
「日光東照宮の門は一つだけ柱の唐草模様が逆に描かれている。そのゆえんは、完璧な建造物は縁起が良くないと言われていたからだ。私には面接も作文も完璧に書ける天賦の才がある。ゆえに内申も完璧になってしまえば縁起が良くない。」
暴論ですね。でも、それでいいんです。人を傷つけるために言っていたり、迷惑をかけていたりするわけではないんですから。自信をなくすより何倍もいいです。
忘れられない言葉
「最後は執念を持った人が勝つ」という塾長の言葉です。
まず執念とは、自分がいかなる状態でも一つの目標に向かって全力を貫くことです。そして、自分の限界を超えて努力する覚悟を決めるには、自分を動かす力が必要です。私を最後まで導いてくれたのは西高への愛でした。そして、私が愛という武器を持つことができたきっかけが、この言葉でした。
勉強以外に教わったこと
受験は勉強以外のことも必要ということです。
笑顔、明るい振る舞い、全力でやること、真剣さ、元気…。これらはまず内申点という大事な要素に大きく関わってきます。そして、受験だけでなく人として生きていく上で大切なことだと学びました。
後輩に一言アドバイス
先程、西高への愛と書きました。
志望校が好きという感情は思えば当たり前ですが、私は偏差値、テストの点数に追われるうちに忘れかけていた気がします。
受験生の皆さん、挫けそうになったらもう一度考えてみてください。あなたは志望校がどれくらい好きなのか。説明会、記念祭、色々行ったと思います。肌で感じたはずです。熱気、喜び、青春…。それをもってしてあなたは今志望校を決めた。その高校の雰囲気が、生徒が、先生方が、全てが好きだから。
その愛はきっと、あなたと高校を繋いでくれます。だから、その気持ちは絶対に忘れないで。
あなたはずっと努力してきた。過去問にかじりついて、模試見て絶望して、また立ち直って。偉いよ。すごい頑張ってるよ。ヒーローだよ。たとえすぐ報われなくても、その執念はきっといつか花開く。だから大丈夫。信じて進んでください。
Sくん ※推薦合格

入塾のきっかけ
僕が学志舎に入塾したのは、小学6年生の3月です。この塾を選んだ理由は、体験入塾の際に教室へ足を踏み入れた瞬間に感じた熱気でした。全員が目の前の問題に黙々と取り組む姿がとても印象的で、自分の理想像に重なる先輩たちの姿を見たとき、「この塾に入りたい」と強く思いました。
入塾前と入塾後の変化
塾に入ってからは、論理的思考を身につけることができたと感じます。授業の解説の合間に関連事項を話してくださる時間があり、それが特に印象に残っています。
たとえば、学校では「南北問題」という言葉を公民の単元で学ぶだけかもしれませんが、なぜそれが起こったのかを深く考えると、帝国主義や戦争による植民地支配、宗教の影響、伝統文化の喪失、さらには地理的要因として気候など、さまざまな要素が関わっていることがわかります。
このように、一見すると見えにくい事柄について学ぶうちに、世界は単語や事象がただ存在しているのではなく、それぞれが影響し合って成り立っているのだと気づきました。日常の中でも「この背景には何があるのか?」と考える習慣がつき、論理的思考力が鍛えられたと思います。
忘れられない言葉または授業
村岡先生の「今しかできないことをする」という言葉が特に印象に残っています。僕には、公認会計士になるという夢があります。その夢に向けて、現在は簿記の勉強を進めています。受験が終わったばかりで遊ぶこともできますが、それよりも夢の実現に向けて今やるべきことを優先したいと考えました。
「今できる最大限のことをやり、未来の自分を助ける行動をとる」
塾で学んだこの考え方が、今の自分の軸になっています。
授業以外に教わったこと
推薦入試直前の2週間で行われた推薦特訓は、とても楽しく、未来に役立つ時間になったと感じています。
面接練習を通じて、さまざまな先輩方から学校の様子を聞いたり、面接で話す内容を深めたりすることができました。先輩方がいなければ思いつかなかった発想も多く、とても有意義な時間でした。また、学校生活について話を聞く中で、自分の未来を具体的に想像できたことがモチベーションにつながりました。
作文指導では、添削を通じて新たな考え方を示していただき、自分なりの型を確立できたことで、本番では迷うことなく自信を持って書き進めることができました。
後輩に一言アドバイス
僕は、中3の1学期に理科・社会の基礎固めに時間をかけすぎてしまい、その他の教科の過去問でなかなか点数が取れず苦戦しました。点を取れるようになると勉強のモチベーションも上がるので、2学期からの過去問演習の前に、なるべく基礎を固めておくことが大切だと思います。
僕の場合、2学期に英検2級の勉強を始めたことで、一気に英語の点数が伸びました。また、数学や国語についても、夏期講習で配布されたプリントを復習することで、点数を安定させることができました。今振り返ると、1学期のうちに英単語をきちんと覚え、夏期講習で基礎を確実に固めておけば、もっと楽に受験を進められたと感じています。早めに取り組むことの大切さを痛感しました。
受験勉強では、「自分の中の当たり前レベルをより高く持つこと」が大切だと思います。学志舎での経験を活かし、これからも自分を高めていきたいです。
Hさん ※推薦合格
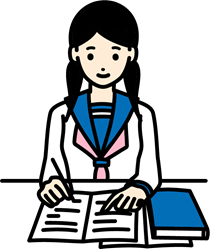
入塾のきっかけ
中学受験が残念な結果に終わった後、高校受験に向けて塾を探していたところ、「絶対に悔しい思いをしたくない!」という気持ちを上手く昇華できそうな学習環境と、母の勧めもあり入塾を決意しました。
最初は先生方や生徒の皆さんの雰囲気に気圧され、やって行けるのかと不安になりましたが、授業に夢中になっていくうちに、中学受験の挫折で塞ぎ込んでいた気持ちが前向きになっていることに気が付きました。
入塾前と入塾後の変化
沢山ありますが、特に「嫌いなものから逃げない力」が身についたと考えています。
中学受験時代は苦手な算数(数学)にあまり向き合うことが出来ず、大きく得点を落としてしまいました。高校受験でも同じようなことが起きるのではないかと心配しましたが、学志舎で数学の解説プリントを渡された時の、その厚みに「逃げないと言うより、逃げられないな。」と感じました。
勉強を進めていく中で、「数学が解ける」という未知の体験が楽しく、自立学習に来たらまずは数学を解いている自分に気づいた時は驚きました。
落ち込んだ時とその回復法
模試でなかなか思うように点数が取れず、塞ぎ込んでしまうことが多くありました。その時に行っていたのが、「決意を声に出して周りに伝える」ということです。
普段から、どんな結果だろうと志望校を変える気はないと親に言っていました。推薦入試直前の結果がD判定だった際、ここで決意しなければ踏ん切りがつかないと思い、結果を返却して頂いた先生に「西以外に行く気はありません。」と伝えました。今思うと、他の人に伝えて逃げられなくするというよりも、自分の思いを言い聞かせて、覚悟を決めていたのだと思います。
忘れられない言葉
学志舎で過ごした全ての時間が宝物なのですが、私の心に深く刺さったのは、塾長が雑談の流れでサラッと口にされた「NGワードは『でも』と『ただ』だ!」という言葉です。苦手なものから逃げがちだった私が自分の最大の課題に気付かされた言葉で、メモ帳の中でも特に濃く書かれ、何重にも線で囲まれて残っています。
また、推薦特訓で山田先生に作文を添削していただいた際の「作文、すごくいいね!」「合格したこれまでの先輩と比べてもトップレベルの作文力」との言葉は、自分が大好きな文章という分野で評価していただけたということもあり、強く心に残っています。
「中学受験の作文練習が、今に活きてきている」と言っていただいた際は、自分の今までの努力が決して無駄ではなかったのだな、と報われたような気持ちになりました。
勉強以外に教わったこと
自分の信念を貫くということです。実際に伝えられたわけではないのですが、どれだけ模試や過去問で思わしくない点数を取ろうが、学志舎の先生方は一度も私が西高を受験することを否定したことがありませんでした。どのような結果だろうと、行きたいものは行きたいんだという私の気持ちが応援されていると感じました。
後輩へ
信じられないくらい強く志望校への思いを持ってください。中1の時に西高に訪れた時から、西高に行きたいという思いが一度も揺らいだことはありませんでした。志望校を決定する時期は人によって違いますが、どの時期に決めたのであれ「志望校に行きたい!」という気持ちがあれば、受験を乗り越えていけると思います。
周りへの感謝を忘れず、学志舎で得られるものを大切にして突き進んでください。応援しています。
Sくん ※推薦合格

入塾前と入塾後の変化
塾に入る前は内申がそれほど高くなかったですが、塾に入った後は42まで内申がupし、2年生の頃と比べて8伸びました。また、学校のテストの点数も、目に見えて伸びが実感できました。
落ち込んだ時とその回復法
落ち込んだときには勉強をしましょう。自立学習に行けば落ち込んでいる暇はなくなります。
忘れられない言葉または授業
先生方が授業の合間にして下さる雑談がとても好きでした。過去に行ったお店の話、●●町の■■の話、面白い失敗談などなど。真剣な授業の中に時々出てくるユーモアもあり、最後まで授業を楽しむことができました。
後輩にアドバイス
私が信条にしていることの一つに、自分を貫くというものがあります。学志舎には優秀な生徒が多くいます。その生徒と自分を比べ、焦りを感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、大事なのは他人と比べてどうかではなく、自分が志望校に受かれるかです。前回過去問を解いた時より成長できているか、合格最低点を取るにはどうしたらいいか、そこだけ考えて勉強していればきっと合格に近づきます。他人に左右されず、最後まで自分のなすべきことに向かっていってください。
Kさん ※推薦合格

入塾のきっかけ
私はバイオリンを習っており、高校は音楽高校に進学する予定でしたが、中3の9月下旬に急遽方向転換をすることになりました。慌てて塾を探していた際に、たまたま学志舎のブログを見つけました。翌日体験に行き、その日に入塾を即決しました。
塾に足を踏み入れた時、生徒全員が黙々と集中して勉強していたのが印象的でした。布施塾長と山田先生のお話が面白く、母と笑いながら聞いたことを覚えています。入塾のタイミングが遅く不安しかなかったのですが、塾長と山田先生の「大丈夫!今からでも十分間に合うよ!」という言葉に後押しされ、「ここで頑張ってみよう!」と思いました。西高をはじめとする圧倒的な都立の合格率と推薦特訓に力を入れている点に強く魅力を感じました。その日から約4ヶ月間お世話になりました。
入塾前と入塾後の変化
入塾前はバイオリンに専念していたため、必要最低限の勉強しかしていませんでしたが、入塾後は毎日学志舎で勉強し、1日の時間の使い方が大きく変わりました。先生方に内申upの秘訣を教えていただき、一つ一つ実践していった結果、内申点を41から45に上げることができました。
平日は4~5時間、土日は10時間近く学志舎で過ごしましたが、毎回一瞬にしか感じませんでした。それくらい、学志舎は集中して勉強できる環境だったと思います。4ヶ月間、毎日が充実していて本当に楽しかったです。
落ち込んだ時とその解消法
過去問を解くスピードが他のみんなより遅く、初めの頃は落ち込みましたが、先生方に分からないところを丁寧に教えていただき、日に日に不安がなくなりました。
また、推薦特訓では作文のテーマの解釈がズレてしまったり、集団討論でみんなに圧倒されて発言できなくなったりしたときがありました。そんな時に村岡先生をはじめ、他の先生方や先輩方にも相談をし、具体的なアドバイスをいただき、毎回自信を取り戻すことができました。
忘れられない言葉または授業
毎回の授業全てが面白かったです。先生方が小話をしてくださり毎回のように笑っていましたし、仲間に刺激を受けることができるとともに、自分の「終わりました!」を言うタイミングが早くなっていくことのやりがいを感じ、毎回の授業を楽しみにしていました。
推薦特訓の初日に塾長が「チーム学志舎で頑張ろう!」とおっしゃっていました。また、推薦特訓の最後に行う声掛けも、みんなで合格しようという気持ちが高まると共に自分を奮い立たせるような言葉でした。
勉強以外に教わったこと
学志舎に入ったことで学校以外の先生方や先輩方と話す機会ができ、自分の視野や世界が広がり楽しかったですし、様々なことを教わり、目から鱗が落ちるような発見が多かったです。
学志舎には、学業面はもちろんですが、人間性や生き方を目標とする先輩方が沢山いて、こうなりたいと思える先輩方に出会え、私も推薦特訓などで後輩の受験生の力に少しでもなりたいと思うようになりました。
後輩へアドバイス
たとえ自分では難しいと思う学校でも、妥協せずに、本当に行きたいと思える学校を目標にしてください!先生方の言葉を信じて、一日一日を大切に過ごしてください。学志舎の恵まれた環境を最大限に生かして、通える最後の日まで走り抜けてください!いつの日か学志舎で皆さんと会える日を楽しみにしています。応援しています!!Make the impossible possible!!
Nくん

入塾のきっかけ
私がこの塾への入塾を意識したのは、2年生の冬休みです。1年生の頃にブログを見つけて、その頃から塾の存在自体は認識していたものの、当時は家から近い他塾に通っていました。
しかし、その塾に通ううえで、集中できる環境ではなかったり、思うように成績が上がらなかったりしたため、学志舎への転塾を検討しました。体験の際の面談で塾長と話した際に、学志舎の受験に対する熱量を感じ、入塾を決意しました。
入塾前と入塾後の変化
私は入塾する前は、素内申が40にもとどかず、模試での偏差値も60程度でした。
しかし、入塾後、学志舎の環境をフル活用し勉強することで、仮内申では44をいただき、V模擬での偏差値も70を切らずに安定した成績を取り続けることができました。
また、入塾前後で私が大きく向上したものは、成績だけではなく、勉強体力です。入塾前は頑張ろうと思っても1日5~6時間の勉強で満足していました。学志舎入塾後は、頑張っている周囲の塾生に影響を受けながら勉強をすることで、長時間集中して勉強することができるようになりました。
この勉強体力は、物事に取り組む際に長時間集中して取り組むことができるという面で、勉強以外にも応用することができるため、自分にとっての大切な財産となりました。
落ち込んだ時とその対処法
夏休みや冬休みなどの長期休みは特に、勉強時間が長く、辛く感じることがあるかもしれません。しかし、私の場合は友だちを作り、休み時間に話したり、近くの公園でサッカーをするなどしてリフレッシュを行うことで、勉強を頑張りきることができました。
推薦入試
私は推薦入試を受験しましたが、不合格となりました。推薦特訓では、自分と向き合うことができ、たくさんの同じ西高校志望の友達とも出会いました。推薦入試は不合格で終わったものの、推薦特訓を受けたことに後悔はないと胸を張って言えます。
また、一度不合格を経験したことで、精神的に大きく成長することができました。
先生からかけて頂いた言葉
推薦入試で不合格となり、落ち込んでいるときに先生方から掛けていただいた言葉が印象に残っています。特に、同じ境遇を経験した山田先生には、多くの言葉をいただいて、とても励みになりました。これらがあったからこそ、一度不合格を味わったものの、自信を持って入試本番を迎えることができたと思っています。
勉強以外に得られたこと
私は学志舎で、新たな価値観を得ることができました。塾長や村岡先生などの雑談では、先生方の価値観がよく伝わるようなエピソードを聞き、自分の物事に取り組む際の姿勢などを考え直すきっかけになりました。
後輩へのアドバイス
勉強をしていくうえで、努力をしているのに思ったように結果が出ないと言ったことがあるかもしれません。しかし、そこで踏ん張り、頑張り続けることができる人こそが、最後に合格を勝ち取れる人です。
過程に対する後悔を無くせるように、自分自身が納得できるような努力を続けることができれば、合否に関係なく大きく成長すると思います。しかし、どうせ受験するなら合格してほしいと思っています。心から応援しています!
Yさん

入塾のきっかけ
私が学志舎に入塾したのは中2の時でした。それまでは他の大手塾に通っていたのですが、雰囲気が自分と合わず、母に相談し退塾しました。その後、母の勧めで学志舎の入塾テストを受けに行き、中3の先輩方の黙々と勉強する姿に惹かれて入塾を決意しました。
入塾前と入塾後の変化
入塾前は、勉強に対する熱意や具体的な目標を持っておらず怠惰に過ごす毎日でした。家で勉強する習慣は全くなく、学力テストの結果は毎回散々でした。中3になり友達が受験勉強をしていく中で焦りはじめ、学習意欲が高まっていきました。
私には嫌なことから逃げる悪い癖があるので、学校から直接学志舎に行くことで限りある時間をより多く受験勉強に費やせました。学志舎は平日16時から22時まで自習室を開放しているので家では勉強できない私にとって本当にありがたかったです。また、周りの仲間の熱心な姿に刺激を受け長時間の勉強が出来るようになりました。さらに家でも少し頑張ってみようかなという気持ちが自然と生まれ家庭での学習時間も確保することができました。
このように、入塾したことで自分から机に向かう習慣がつきました。
落ち込んだ時とその回復法
中3の時、難関クラスに入ったものの、もともと様々な人から勧められていた小金井北を目指していました。しかし、西高の卒塾生の先輩が来てくださった日から憧れを持つようになり、西高に行きたいと思い始めました。卒塾生の先輩達との繋がりも学志舎の魅力だと思います。
自立学習を始める前の偏差値は50台でした。そこから諦め半分のスタートだったので、授業中周りの塾生は出来ている問題が自分は出来ない、自分だけ英文を読み終われない、そして過去問の点数は酷いもので、事あるごとに泣いていました。
そのようなときの私の回復法は2つあります。
1つは負の感情に負の感情をさらに重ねることです。例えば、出来なかったことを思い出し自分の出来の悪さを再確認したり、さらに失敗したときの様子を思い浮かべることで、「出来ないからやるしかない」という気持ちで落ち込んだ気持ちを勉強にぶつけることが出来ました。
もう1つは、自分の気持ちを書き出すことです。自分の感情をアウトプットすることで感情を客観的に捉えられ気分がすっきりして勉強に集中できました。
忘れられない言葉
私が忘れられない言葉はたくさんあるのですが、特に印象に残っているのは布施墊長の「人と違う結果が欲しいなら、人と違うことをするしかない!」という言葉です。この言葉を聞いて今まで何もやってきていなかった自分が今から人並みなことをしても追いつかないに決まっているのに何甘えてるんだと我に返りました。
その日から通学中は家を出てから学校につくまでずっと英語の速読をしていました。満員電車で学志舎オリジナルプリントができないときはスマホで写真に収めて勉強を続けました。何かと小さなことを理由にして勉強を中断していた私からは想像もできない成長ぶりでした。そして毎日の積み重ねでどんどんリーディング力が上がっていきました。
また、12月の模擬でD判定をとってしまったとき、塾長が言ってくださった 「君ならできる!」という言葉が心に刺さっています。正直だめだと思っていたのですごく衝撃的でしたが、真っすぐな言葉に突き動かされ、冬期講習中、理社に必死で取り組みました。学志舎の強みである圧倒的な過去問演習により、理科を36点から 96点に上げることが出来ました。
勉強以外に教わったこと
私が勉強以外に教わったのは「礼儀」です。学志舎では教室の出入りの際に「こんにちは」「ありがとうございました」と挨拶をします。また人生経験豊富な塾長や村岡先生の勉強になるお話をメモする習慣もつきました。
他にも消しゴムのカスを残さないなど、人への配慮を意識した行動をとることの大切さを改めて再確認しました。これは社会に出たときにとても役立つことだと思います。
後輩のみなさんへ
受験生になると毎日が忙しく辛いと感じることがあるかもしれません。しかし、いざ受験が終わると案外何もなかったように感じます。合格発表の日まであの単元復習しておけば良かったと後悔ばかり生まれてきます。後悔しないために学志舎の環境を無駄にせず頑張ってください。
冬になっても失敗してしまい思うようにならないこともあるかと思います。それでも山田先生の「手は動かし続けてください。」という言葉のように、くじけそうになっても勉強はし続けてください。学志舎の先生方は私たちの志望校への最短ルートを教えて下さります。それに沿って努力を積み重ねれば合格できると思います。このようなアドバイスですが、後輩のみなさんのお役に立てれば幸いです
Hくん

入塾のきっかけ
私が小学5年生の時、親から自分に合った塾として紹介されたのが学志舎でした。初めての塾ということもあって楽しみよりも不安が勝っていましたが、外からドア越しに見た時、全員が机に向かって黙々と勉強している光景に圧倒されたのを今でも覚えています。
学志舎に入塾し、都立中受験に挑戦しましたが、残念な結果に終わりました。しかし、今でも全く後悔は残っていませんし、この経験は自分の糧となってくれました。その後中学生となった時に、再入塾するか決める場面がありましたが、そこでは先生方への信頼も十分にあったため、自分の意志で再入塾を即決しました。
内申up
内申の取り方を早いころから教わることができたため、1年生のころからコツコツとテストの点数や提出物の評価を向上させていき、素内申を1年生はじめから2年生末にかけて36から44まで上げ、受験期までその内申をキープできました。オール5を目指していたため悔しい気持ちもありましたが、そこは割り切って気持ちを切り替えられました。
また、入試を終えて確実に言えることとして、内申点のアドバンテージは、思っている以上に必ず気持ちの安定剤となります。早い時期から学志舎に通い、内申upを目指すことをお勧めします。
落ち込んだ時とその回復法
私は、都立高推薦入試に落ちたときにかなり落ち込みました。推薦合格率の高い学志舎で残念な結果を目の当たりにしたとき、これからどうしようとかなり焦りました。そこで、その後の面談まで負の感情をすべて吐き出そうと決めました。それは、学志舎の先生方と顔を合わせれば自然と安心し、気持ちの切り替えが出来るという信頼を持つことができたからです。
そのようにして気持ちが落ち着き、周りに推薦合格塾生がたくさんいても自責の念を捨てて集中して勉強できました。
勉強以外に教わったこと
私は、この学志舎で「あきらめない執念」を学ぶことが出来ました。この5年間の中で「都立中受験」と「都立高推薦受験」という2度の挫折を経験しました。しかし、最後までこの「学志舎」という良質の環境で最大限集中して努力し続けた結果、最後の土壇場で執念と意地を見せて合格を勝ち取ることができました。今となってはその2つの経験が私にとって貴重な財産だと思うことができます。
だからこそ、私はこの先何かに挫折してしまった人の気持ちに寄り添っていきたいと思います。それもこの学志舎で教わることができるものなので、後輩たちにも他人の気持ちを推し量れる人になってほしいです。
後輩へ
悔いのない取り組みを行ってほしいです。高校生になって、どんな結果になったとしても、後悔しないほど頑張ったという体験が何よりも重要だと私は思います。そのために伝えておきたいことを話します。
まず、中1生、中2生でもできるものとして、内申は取れるだけ取っておきましょう。早い段階から高い評価をいただいた方が、先生方の信頼を獲得しやすいですし、後々頑張っておいてよかったと思う日がやってきます。
また、中3で推薦特訓を受講する方は、絶対にその中で遠慮はしないでください。短い期間でうまくなるには、常に成長しようと貪欲になり続ける必要があります。ほかの人に譲ろうと遠慮したら負けだと思うくらい、貪欲に推薦特訓を受けてほしいです。
最後に、自分より凄い、尊敬する人を同じクラスの塾生の中で見つけておきましょう。そうすることで、その人に近づこうと努力することができ、毎日頑張ろうとする原動力がわいてきます。
せっかくの学志舎の最高の環境を活かさないのはとてももったいないです。最大限活用し、学志舎生のみんながそれぞれ目指す志望校に合格することを願っています。
Kくん

入塾のきっかけ
西高に進学した兄が学志舎に通っていたので入塾しました。兄の影響もあり、僕も西高を目指すようになりました。
入塾前と入塾後の変化
長時間勉強できるようになりました。以前はすぐスマホを触ってしまいなかなか勉強できませんでしたが、塾で机に向かうことが習慣化したことで長時間勉強できるようになりました。
そのおかげで定期テストなどで学年1位を取れるようになりました。学志舎は勉強する上でとてもいい環境だったと思います。
落ち込んだ時とその回復法
受験前最後の模試で過去最低偏差値を出してD判定となり、少し落ち込みました。そこで私は、西高で楽しむ自分を想像して気を持ち直していました。また、過去問の出来については手応えがあったのであまり心配はしていませんでした。
忘れられない言葉
塾長が事あるごとに仰っていた「執念」という言葉です。
その言葉に刺激され、西高に受かって見せるという気持ちをずっと強く持っていました。中3の夏くらいからは受かるとしか思っていませんでした。「信じるものは救われる」ということだと思っています。
勉強以外に教わったこと
これから先どのように生きていけばいいのかを教えていただきました。例えば、村岡先生が仰っていた「●●の掛け算」や「魅力的な社会人とは何か」など、多くのことを教えていただきました。他の塾では学べない貴重なものだったと思います。
後輩へのアドバイス
数学
計算ミスが多くて悩んでいましたが、ある程度数字を綺麗に書くようになってからミスはほとんどなくなりました。そして、他の教科にも言えることですが、自分は天才ではないことを認め、捨て問は潔く捨てましょう。限られた時間内にできるだけ得点を取って合格最低点を取ることが目的です。
英語
学志舎オリジナル長文プリントを読むときはぜひ口を動かしてみてください。声に出さなくてもいいです。僕は塾で口を動かして読んでいました。黙読とは感覚が違います。
暗記
理社などでどうしても覚えられないところがあった時は毎日触れるようにしていました。そうすれば嫌でも覚えます。村岡先生が仰っていましたが、単純接触回数を増やすことは大事です。
過去問
過去問を3教科連続で解かなかったり、解いている途中にタイマーを止めてトイレに行ったりする…当日はそれでいいのでしょうか?僕は眠くても体調が悪くても必ず3教科連続で休憩は1~5分で解くようにし、常に当日を意識していました。辛い時こそ勝負です。
また、学志舎の過去問演習量は圧倒的だと思います。僕は3教科を70年分解きました。過去問を解いた量は自信にしていいと思います。
早いうちに
今だから言えることですが、中3の2学期の途中までは勉強を少しサボっていました。サボった分は必ず返ってきます。後々キツくなるのでたくさん自立学習に行って他の人と差をつけましょう。受験前の最後の1ヶ月の勉強量は普段の3ヶ月分くらいだった思います。よく頭が痛くなっていました。
納得するまで
わからないことをそのままにしてしまうのは残念です。当日自分が後悔しないように徹底的に突き詰めましょう。
睡眠
朝起きるのが苦手で受験の1ヶ月前くらいまでは毎朝ギリギリに起きるという感じでした。講習期間中は毎朝自転車を飛ばしてギリギリに到着。席は一番後ろでした。こうならないように、できるだけ早く朝型にすることをお勧めします。
Nくん

入塾のきっかけ
どの塾に入ろうか悩んでいた時に、知人に学志舎を勧めてもらいました。体験時の面談の時から、塾長の圧倒的なカリスマ性と塾生を想う気持ちが伝わり、最終的に学志舎に入ることを決めました。
入塾前と入塾後の変化
学志舎に入って大きかったのは、勉強に集中できる環境を手に入れたことです。学志舎に入る前は塾に通っておらず、学校以外で勉強をする時間はほぼありませんでした。
しかし、学志舎の教室に行けば、周りの塾生が集中して勉強しているので、自分もやるしかないという気持ちにさせられます。
落ち込んだ時とその回復法
私が一番落ち込んだのは、12月の模試でD判定をとった時です。その時はもう志望校を諦めるしかないのではないかと思い、焦りと不安で胸が一杯になりました。
そのように私が落ち込んでいても、学志舎へ行けば先生の言葉に励まされ、他の塾生に刺激を受け、しっかりと勉強に向き合うことができました。
勉強以外に教わったこと
受験勉強以外のことも、学志舎では多く学びました。入塾時は塾生全員が威勢よく挨拶していることに驚きましたが、学志舎へ通ううちに、気づけば自分も周りと同じように挨拶するようになっていました。
また、先生方が授業で話してくれる豆知識や笑い話、人生経験を聞くのが楽しみで、塾で勉強を頑張り続けるモチベーションになりました。
後輩へのアドバイス
後輩へのアドバイスは、自分の本当の実力を信じることです。うまくいかない時や失敗した時には、自分はまだまだこんなものではないと思ってください。入試直前になっても、自分が合格しないわけないと心から信じられれば、それほど強いことはないです。ぜひ後悔のない中学校生活を送ってください。応援しています!!
