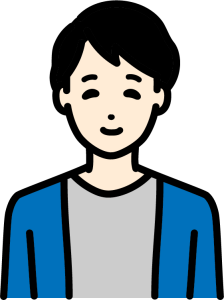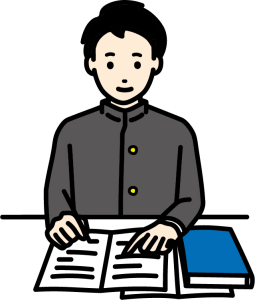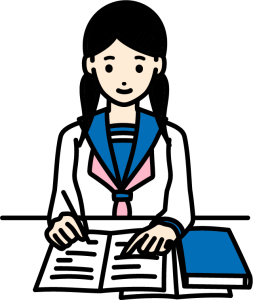合格体験記&親御様メッセージ(2025年 都立三鷹中:Kさん)
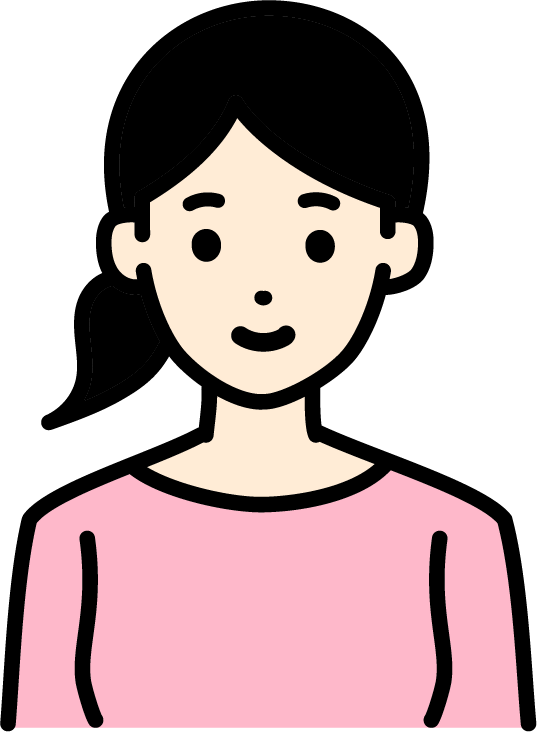
Kさん
入塾のきっかけ
周りの友人の多くが受験する予定で、自分は受験しなくて良いのかという迷いの気持ちがありました。家族は私が公立中に行くと思っており、受験は考えていない様子でした。
私が受検しようと考えたのは、祖母のおかげです。はじめは「受験したら?」などという軽い言葉でした。「あなたならきっとできる」などという励ましの言葉もあり、その言葉を信じて受検することを決めました。姉が学志舎に通っていたこともあり、塾に行くなら学志舎という雰囲気で、塾選びは即決でした。
入塾前と後の変化
入塾前は学校の授業にはぎりぎりついていけていたくらいでした。特に算数が苦手で、点数が低いことも多々ありました。また、集中力もありませんでした。読書がもともと好きだったため、本を読んでいる間は集中できていたのですが、読書以外となると集中ができず、すぐに本を読み始めてしまうことが多かったです。(一方で、そのおかげで文章に対する抵抗が全くなくなり、適性Iが得意になったことで他の受験生と差をつけられたと思います。)
入塾後は、やる気に満ち溢れていました。三鷹中に行くことを目標とし、はじめの勉強量は少なかったものの、着々と努力を続けていました。
その後、やる気は失せ、勉強も上手くいかず、どうすれば良いのかわからなかった時がありました。それは、小6の春頃です。小6生になっても、気持ちはまだ小5生のままで、学年が変わったからといって一段とやる気が出たというわけではありませんでした。
しかし、共に頑張る仲間を見つけたことで、夏期講習では毎日塾に通い、自分を奮い立たせていました。また、冬期講習からは徐々に焦りの気持ちも持ち始め、8時半から18時まで塾にいるという日々を過ごし、充実した時間を過ごしていました。仲間と切磋琢磨することで得られた、この充実感と充実した時間は、何にも代えがたい私の宝物です。
落ち込んだ時とその回復方法
適性IIの過去問をいくら解いても新しい過去問ではあまり点数が取れないことに落ち込みました。また、たくさん過去問を解いており、直しも行っているのに、新しい他の学校の過去問になると全く手がつかないことに自分自身に不満を抱いたり、本当に受かるのかという不安があったりしました。私はそのことを佐藤先生に相談しました。すると、佐藤先生は直しを繰り返し行うという私の勉強方法を肯定し、「初見で高得点が取れなくても落ち込む必要はない」と言ってくださり、不安が解消されました。
落ち込んだ時は、まず先生方に質問すると良いと思います。何事にも親身になってくださり、私にとってベストな回答をくださりました。
印象に残った言葉
私の印象に残った言葉は、佐藤先生の「最後の1秒まで手を動かそう!」、山田先生の「文理バランスよく勉強できたことを自信にしよう!」、そして、塾長の「自滅しなければ合格できる!」という言葉です。
当日、適性Ⅱの大問1の最後の問題で答えが出ず諦めかけていた際、この佐藤先生の言葉を思い出し、ベストを尽くせるよう手を動かそうと思うことができました。最後の最後まで手を動かしたことは、答えがあっていなかったとしても、記述の部分点等で良い結果につながったのではないかと思います。
山田先生は、私が適性Ⅱに比べて適性 Iの仕上がりに不安を抱いており、心配であることを相談すると、適性 IとⅡのバランスをわかりやすく教えてくださり、自信も与えてくださいました。そして、前日提出した作文の添削の締めに先ほどの言葉を書いてくださいました。山田先生の言葉は、心に響くことが多々ありました。
塾長の言葉から、私は適性Iで作文を何度も読み直し、常に直すべきところを見つけるという思いで作文を書いていました。はじめは、採点官の心に突き刺さるもの、他者とは異なるものを書こうとすると思います。しかし、それ以上に大切なのは、漢字や文章の使い方などの初歩的なミスをせず、減点されない作文を書くことです。そのことを心に留めて作文を書くようにしていました。
勉強以外に教わったこと
勉強以外に教わったことは、毎回塾を出入りする際の挨拶です。通塾前は、あまり挨拶をすることはできませんでしたが、学志舎で毎日挨拶をすることが習慣になり、塾内だけでなく、家の近所の方、入試の際にも先生方に挨拶を自然とすることができました。
後輩へ一言アドバイス
私は、先生方にはわからないこと、気になることはすぐに質問し、疑問点をそのままにしないことが大切だと思います。なぜなら学志舎の親身になってくださる先生方のおかげで不安な点、疑問点はすぐに解決するからです。
また、適性 Iの作文では冬期講習で山田先生が読んでくださった、一年前に合格された先輩の作文を三鷹中の入試中の構成メモを考えている際に思い出し、それを参考に書きました。学志舎の先輩の作文例は、いざという時に使うことができ、とても便利なので、メモをしていつでも使えるよう、自分の引き出しを増やしておくことが大切です。私は適性Ⅱがとても苦手でしたが、最後の追い込みで様々な過去問を繰り返し解いたり、家で仕事から帰ってきた父に教わったりし、自信をつけていきました。
そして、本番で慌てないようにするために、事前に本番と同じように学校まで行き、帰宅して同じ時間帯から解き始めるということをしました。これにより、一度イメージトレーニングができたので、本番も焦らず臨むことができます。
これから先、受験生になるにおいて不安になることがたくさんあると思いますが、毎年先輩方はその不安を経験しているはずです。憧れの先輩や、この人となら頑張れるという仲間を作ると、不安や心配もやわらぎ、気持ちを奮い立たせることができるでしょう。私もそうであったように、合格するチャンスはみなさん平等にあります。これからも、努力を劣らず合格に向けて勉強を続けてください。三鷹中等教育学校から応援しています!
親御様
学志舎を選んだ理由
上の子供が学志舎に入塾していたからです。学志舎のブログから先生方のお人柄を想像し、入塾テスト時の布施塾長の言葉から、我が子を任せられる、心の成長を育む塾だと判断しました。
受験を決めた
受験することを決めたのは、子供自身でした。親もですが、子供の覚悟も大事だと実感しました。自ら受験したいと言った我が子ではありましたが、入塾後、段々と勉強をしなくなり、本当に受験するのか?と気を揉むことも度々ありました。我が家では、娘の自筆の志望動機をリビングの見えるところに貼り、当時はどんな気持ちだったかを、いつでも振り返ることができるようにしました。
親のチカラupセミナーに参加した時の感想
私自身、日頃から子供の話をよく聞いていると思っていましたが、そんなことはありませんでした。親として子供と向き合っていないことが分かり、顔から火が出る思いでした。自分の子供を全く理解していない、大人目線の考えだと気づかせてくれるものでした。
学志舎の先生は子供のことをよく観察しており、思いやり、やる気を引き出す「信頼できる先生」だと思いました。
受験期における子どもの成長
娘は適性Iの作文を毎日のように書いていました。入試まで150枚以上の作文を書いて添削いただきました。本を読むことが好きな子供なので、作文を毎日書くことは苦ではなかったようです。
受験を意識してニュースを見ることが増えたため、時事にも詳しくなり、知識も増え、精神的にも成長したと思います。
受験直前期の親の関わり方
直前期は、特に父親が積極的に子供に勉強を教えると、塾とは教え方が異なり、子供が混乱するということがあるそうです。私もこのことを知り、子供から求められれば教えましたが、それを求められた際も、学志舎の先生からどう教わったかを確認の上で、その内容をイラストにしたり、理解しやすいように表現するように努めました。適性Iは学志舎の先生に完全にお任せしました。
学志舎に感謝
塾長はじめ先生方には、感謝しかありません。学力だけでなく心の成長も育んでいただきました。卒塾となりますが、あと数年通わせたいと思える塾です。
学志舎のさらなる発展と、先生方のご健康を心よりお祈り申し上げます。