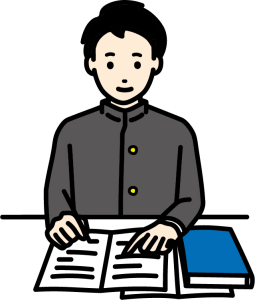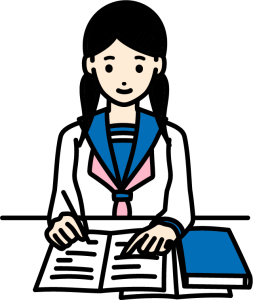合格体験記&親御様メッセージ(2025年 都立西高校:Nくん)※推薦合格
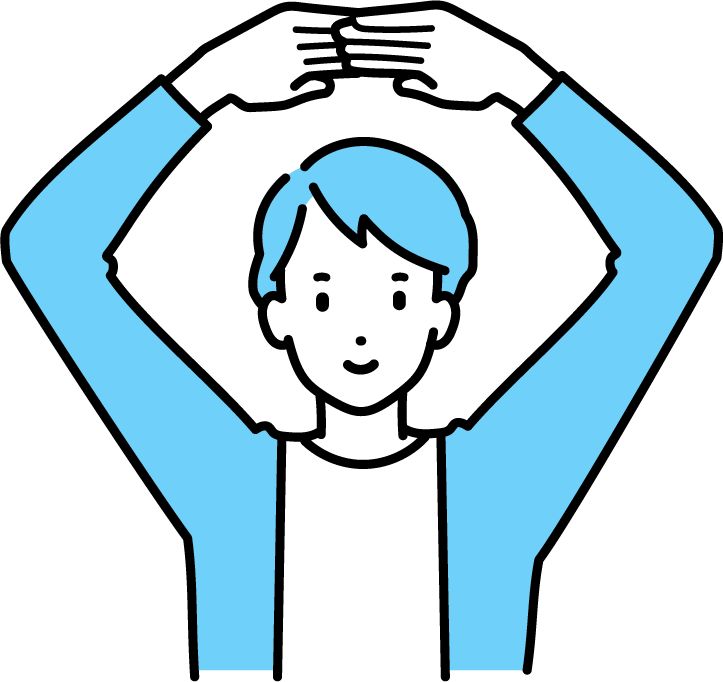
Nくん
入塾のきっかけ
小学生のとき、都立中受験をするために他大手塾に通っていました。しかし、塾の方針に自分が合っていないと感じることが多々あり勉強のパフォーマンスがよくありませんでした。
都立中が不合格と分かった日から、高校受験でのリベンジに向けて「自分の学力を最大限高められる塾」を家族で探しました。その時に、姉の友人が通っていた塾として「学志舎」が候補に挙がりました。「勉強が苦手な人でも勉強に集中して取り組める塾」と聞いて、体験に行きました。
初めて学志舎の教室に入ったときに、全員が喋らず、黙々と学習に取り組む姿に大きな衝撃を受けた記憶があります。「ここなら私でも集中して学習に取り組めるのでは…?」と思い、入塾を決めました。
入塾前と入塾後の変化
「人の話を聞く姿勢」が身に付きました。学志舎では当たり前のことになっている「背筋をのばす」「相槌を打つ」「目を合わせる」という行動は人の話を聞く上で非常に大切だと思います。
また、集中力が格段に上がりました。入塾したての頃は学習を1日30分できるかどうかすら怪しいレベルでした。しかし中3の夏期講習では授業終わりの15時から自習終了時間の19時まではもちろん、長い日は20時過ぎまで自習したことがありました。勉強が苦手な自分をここまで集中させられる学志舎の自習環境は本当に凄まじいです。
学志舎での授業
布施塾長の授業では、実際の試験の時に役立つアドバイスやこれから生きていく上で役立つ考え方を毎回学ぶことができ、前向きになれました。解説はスピーディーなのにとてもわかりやすく、1回の授業で非常に多くの学びを得ました。また、塾長の「人と違う結果が欲しいなら、人と違うことをするしかない」という言葉は自校作成校を受験する上では非常に大切だと思います。この言葉のおかげで努力することができたといっても過言ではありません。
村岡先生の授業では、社会や国語のおもしろい豆知識をはさみつつ、論理的な解説がされていてわかりやすかったです。自己PRカードの添削や推薦特訓では自分の性格や特技、将来の夢などについて深く考え「これからどう生きるか」を考える機会になりました。コミュニケーション講座では、相槌の効果など「コミュニケーションの上で重要なこと」つまり「これからの人生で必要な力」について学ぶことができました。
そして中1、中2のときにお世話になった先生方の授業でも細かくわかりやすい解説がある上に、「おもしろかった最近の話」「理科分野の豆知識」「高校受験の時の苦労」など、ためになりかつ面白い雑談があり、非常に質が高かったです。
勉強はもちろん、人生観や豆知識も学べる学志舎の授業は唯一無二だと思います。学志舎の授業で得たことを今後の人生で活かしていきたいです。
後輩へのアドバイス
私の場合、体調が悪くなる日が多く、学志舎に行けない日もありました。そのため「元気な日は必ず学志舎に行くようにする」「行けなかった日は英単語や歴史の年号などの暗記をする」というように、できるときに最大限努力することが大切だと思います。
親御様
第一希望の東京都立西高等学校の推薦入学試験合格まで、3年間熱意のこもった丁寧なご指導をいただきありがとうございました。
他塾ではなく学志舎を選んだ理由
息子は小学校3年生から姉の影響で中学受験を目指し、4年間大手進学塾に通塾しました。しかし、大手進学塾ではたくさんの教材やテストが与えられ、ひたすらそれをこなす環境では、本人のやる気を持続させることが難しかったです。
結果として高校受験を目指すことになった時に、あらためて塾選びを行いました。通塾していた塾とのミスマッチを感じ、他の大手塾は広告媒体等で情報があるものの、ここなら頑張れそうと感じる塾が見つかりませんでした。
そんな中、姉の中・高の友人が学志舎出身で名前を聞いており候補に挙がりました。入塾説明を受け、高校受験に向けたスタートは学志舎に決めようと両親・息子3人即決で一致しました。
決め手は、対応いただいた村岡先生に感じた進学塾の指導者としての信頼感と実績に基づく説得力、入塾説明に伺った際に自習されていた当時高校入試を控えた塾生の皆様から感じる気迫でした。
この先生と塾生全体の環境が唯一無二のもので、世の塾は「学志舎か学志舎以外」であると感じました。
親のチカラupセミナー参加時の感想
セミナーは受験を控える子の親の気持ちで参加すれば、全てが重要な情報でした。ただ、息子の結果が出た今振り返ると、都立高校を目指す上での内申点の重要性、推薦入試で合格するためのプロセス、目標設定において私立等に分散させることなく勉強時間のリソースを都立高校に振り向ける重要性の3点が特に心に残り、親として意識しておりました。
ただし、内申点については、親の目から見ても息子は定期テスト対策以上に提出物等も期限を守り丁寧に心掛けていたように思いますが、2年生時点で素内申39でした。よって、先輩卒塾生のような素内申44や45は到底到達できない目標だと感じていました。
最終的な素内申は44でした。客観的に分析すると中学3年の担任の先生と息子の相性がよく、それを軸に中学校の先生方とのコミュニケーションがうまく図れたことが功を奏したと考えています。これは家庭教育では得難く、学志舎の先生方とのコミュニケーションを通じて息子が教えていただいた賜物だと深く感謝しております。
受験期における子どもの成長
中学3年から自立学習に積極的に行くようになり、息子の意識の変化に親として嬉しく感じました。しかし、最初に迎えた中間テストの点数はこれまでより芳しくなく、親としてとても不安を感じました。しかし、その結果を一番気にしているのは本人だろうと慮り、努力を称え、期末テストで中間テストの反省点を活かして取り組むように応援しました。
また、推薦特訓については毎日いろいろな学びがあったとのことで、とても楽しみに参加していました。来年度からお手伝いできることを本人はとても喜んでおります。
なお、上記は現時点で振り返って思うことであり、結果が出るまではこれまでセミナーやブログで紹介いただいた、カリスマ性あふれる学志舎卒塾生の皆様と比べて、正直なところ本人の熱意や気合には最後まで不安でした。ただ、推薦合格して息子の気持ちの上での中学受験も終わり、ようやく捨てた大手塾の中学受験教材の未使用感と比べ、学志舎教材の汚れ具合を見て息子の努力を感じました。
見守る親の心境
セミナーでの受験情報以外で一番の学びを感じたことは、「中学生が一日学校生活で疲れた身体で塾にて勉強することは、大人が一日仕事して夜からもう一つ仕事をすることと同じ」というマインドを持つことでした。自分自身も中学生の頃は塾に通い高校受験を乗り越えてきたので、当たり前のことのように考えていましたが、布施塾長の言葉から、今の自分が仕事の後にもう一つ何かできるだろうかと、息子との接し方を考えるきっかけとなりました。
しかしながら、見守る親に徹することができたかについては、夫婦とも反省は残っております。受験直前に、内申点で期待以上の結果が出た後やVもぎで好成績が出ている時に、プレッシャーからメンタル的に落ち込む特性があり、親として理解に苦しむとともに、気が気でないことがありました。ただ、授業でも自立学習でも、学志舎に行ってしまえば、元気になって帰ってくる姿がありました。
親として満点の対応はできませんでしたが、学志舎のセミナーでいただいた「見守る気持ち」を思い出しつつ乗りきることができたと感謝しております。