学志舎が「小6理系授業」で大切にしていること
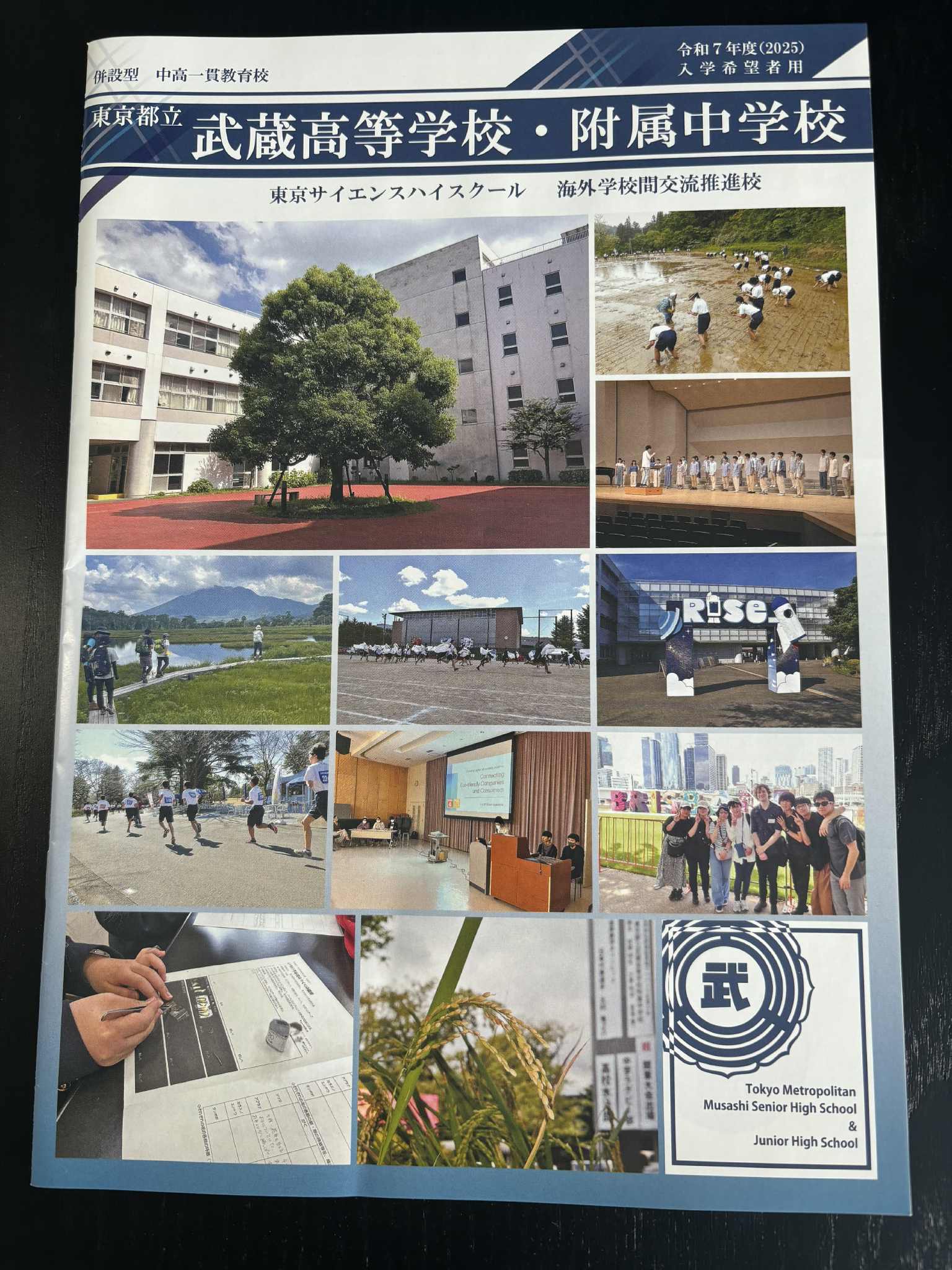
学志舎の小6授業では「問題文(会話)から条件、現象を読み取り、それをヒントに手を動かし試行錯誤していくこと」を大切にしています。1回で答えが出なくても全然大丈夫。書いては消し、書いては消しを繰り返し、粘り強く取り組む子に勝利の女神は微笑みます。
9/14(日)特別授業で解説した都立武蔵中(平成28年度)適性Ⅲの大問1(2)で「~囲まれた図形の面積を44㎠になる~」という条件がありました。この際に足し算をしながら44㎠に合わせていく方法ももちろん考えられますが、1辺2㎝の正方形の面積が4㎠であることを活かし、囲まれた図形の中にその1辺2㎝の正方形が44÷4=11個入るという目処を立てることが有効になります。面積のことは一旦置いて、手を動かし経路図を書いてみる。その後、正方形が11個になるよう調整していくことでショートカットが可能になります。過去問演習を通じて、このような工夫を身につけていきたいところです。
同じ大問の小問3は、立方体の展開図に経路図を書き込み、面積を求める問題でした。今回は重なる辺が限定されるため、それほど時間をかけずに解ける問題となっています。先に重なる辺を1組決めてしまい、経路のミス(同じところを通っていないか?など)がないかを確認したあとは、引き算で面積を出していく。直線上で図形を回転させるような問題ではないので、円周率を使うことなく、計算はラクでした。
できなかった塾生は悔しい気持ちを大切に直しを進めていきましょう。
授業中に何度か伝えましたが、できた人は自信に。できなかった人は悔しさをバネに前へ進んでもらいたいと思います。
本日の過去問演習において「60点という高得点を取ることができたが、直しをしないA君」と「0点という泣きたいような結果になったが、きちんと直しをしたB君」では、どちらか2月3日に合格点を取ることができるか?それは一目瞭然でB君です。
「解説を理解し、線分図やメモで思考を整理し、その流れを記述し、合格点がもらえる答案にする」
そこまでやって初めて、「きちんと直しをした」と言うことができ、間違いなく授業のビフォアフターで比較し自身の学力は高まっています。
9月のこの時期、目先の点数は気にしなくて大丈夫。それよりも「今日の授業で自分は何を身につけることができたのか?」そのことを自問自答できる人であることを切に願います。
大問2の小問1では「日常生活の中で起きている身近な科学に対して、なぜ?どうして?と普段から知的好奇心を持ち、その目で確認または調べる習慣がある人」を都立中の先生方が求めていることがよく分かる問題でした。
同じ大問の小問2では、20℃の水と40℃の水のいずれかを選ぶ問題になっていましたが、「温度のちがう水は、同じ重さだけ混ぜたときに二つの平均の温度になるのですね」というはるき君のセリフがヒントになります。0℃の水に加えた際、結果として10℃になる上で考えやすいのは40℃ではなく、20℃の水。この問題で有効になってくるのが「逆算思考」です。結果(ゴール)から逆算し、10℃の水を作るために、0℃と20℃の組み合わせとし、次に0℃の水を作るために、0℃の氷と20℃の水では重さの比率がどうなるのか?を表1と問題文から読み取る。会話文にあった1対4の比を活用することで、0℃の水の重さが2500gに確定し、今一度、最後の平均で考えるフェーズに戻り、最終的には足し算することで解答できます。(※言葉だけでは分かりにくいので、授業では図解で説明しています)
逆算思考を使いつつ、一方向だけでなく双方向に働かせる。これをまだ小学6年生の段階で求められるのは酷かもしれませんが、間違いなく頭が鍛えられます。単純暗記の知識問題がないため、過去問を1年分解くだけでも脳の疲労は大きいものになります。だから学志舎において、都立中対策の授業は長時間行いません。それは、効率が極めて悪いからです。頭を休めること、本を読むこと、体を動かすこと、家族との会話や友人との会話で何かを感じることなど、教室の外での体験や感性を磨くことも大切にしてもらいたいと思います。











