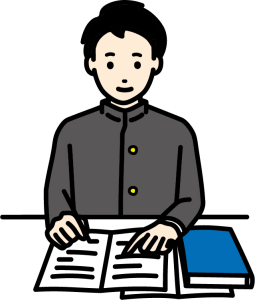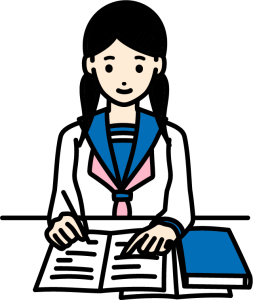合格体験記&親御様メッセージ(2025年 都立武蔵野北高校:Yさん)※推薦合格
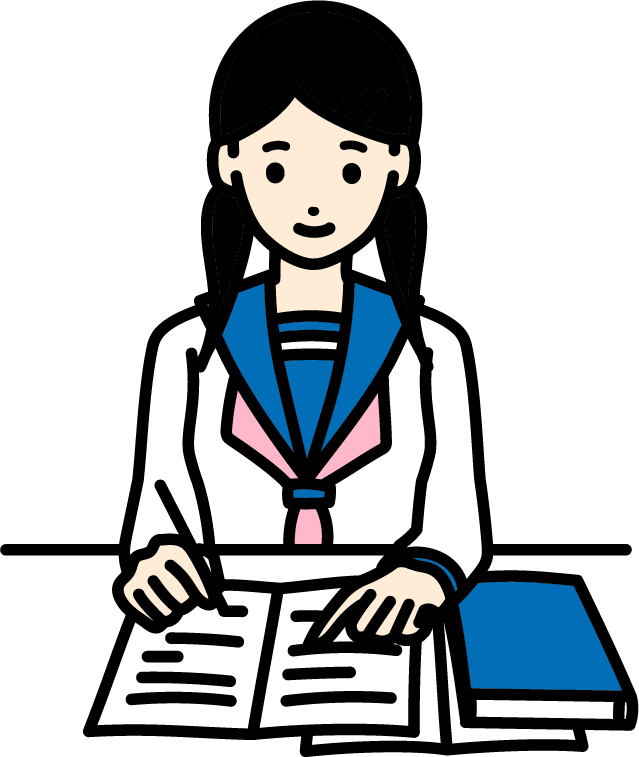
Yさん
入塾のきっかけ
私は都立中受験を経験したのですが、その際は他の大手塾に通っていました。結果は残念に終わりましたが、塾もあまり自分に合っていなかったような気がして高校受験では別の塾が良いと思っていました。
そこで、親が調べてきてくれた学志舎に行ってみると、目に入ったのは、ずらりと並べられた机に向かい塾生みんなが集中して全力で取り組んでいる光景でした。
これまでに見たことのない塾の雰囲気に驚きましたが、直感的にここで受験勉強をしたいと思い、中学2年の夏から通うことになりました。
入塾前と入塾後の変化
中学に入り2年の1学期までは塾には通っていませんでしたが、2年に上がってからは成績が一気に落ち、そこから上げることができず悩んでいました。また、学志舎に入塾したばかりの時は、自立学習の時にスマホが気になってしまい、なかなか集中することができませんでした。
しかし、先生方・先輩方から、授業の受け方のポイントや各教科の勉強の仕方など、さまざまなことを教えてもらいました。教えてもらったことを粘り強く着実に実践していった結果、3年の2学期では内申を3つ上げることができました。
学志舎の素晴らしい環境に身を置いて勉強し、まわりの塾生に感化されたことで、長時間の集中力も身につきました。
落ち込んだ時とその回復法
私はもともと落ち込むことが少なかったのですが、推薦入試直前の推薦特訓の際には、面接に改善点が多いこと、小論文が時間内に書けないことなどと、少し自信をなくすことがありました。克服するためにしたことは主に2つです。
1つ目の面接の場合は、自分の良い点と悪い点を書き出し、悪い点は改善できたと思ったら印をつけていくことです。何事も「見える化」していくことで、目標が明確になったり自分が何をすべきかが分かったりすることがあります。
2つ目の小論文の場合は、初歩的なことですがしっかり時間をはかって練習することです。また、小論文の過去問は学志舎では山のように配られるため、これだけ過去問を解いてきたという事実に自信を持つことも良いと思います。
落ち込んだ時に限らずですが、回復法というと、まずはよく寝て、よく食べて、よくリラックスすることです。きちんと自分を労ってあげることも受験生には大切だと思います。
忘れられない言葉
布施塾長の「人と違う結果が欲しいなら、人と違うことをするしかない」という言葉が、一番心に刺さっています。自分が実践できていたかは分かりませんが、この言葉を聞いてどんな言葉よりもすっと胸の中に入ってきたのが印象的でした。
また「悩んでいるのはひまだから」「やる気不要」は、学志舎だったから学べた言葉だと思っています。悩んでいるひまがあったら塾に足を運べ、やる気はいらない、学志舎に来ればやる気は出てくる。そんなメッセージが込められているこの2つの言葉は、当初は自立学習が面倒だと思っていた私に新しい視点を与えてくれました。
勉強以外で教わったこと
学志舎では勉強の仕方だけでなく、授業の受け方も教えてもらえます。「まっすぐ先生を見る」「笑顔」など、学志舎で学んだことを活かせたからこそ内申を3つも上げることができたのだと思っています。
また、学志舎といったら挨拶。塾に来たら「こんにちは」、プリントをまわす時には「お願いします」「ありがとうございます」、帰る時には「ありがとうございました」。学志舎だったから挨拶の大切さを改めて感じることができましたし、誰にでも臆することなく挨拶できるようになりました。
後輩に一言アドバイス
何度となく受けたVもぎは自分の学力到達度合いを確認するためには有効ですが、結果に一喜一憂することも多いと思います。結果は、良ければ喜ぶ、悪ければあまり引きずらずに次に向けて勉強するというマインドでいたほうが、メンタル安定に繋がります。実際、私は前回より判定が下がっても、前回と比べて良くなったところを探して「ここ前回より上がってるじゃん。成長してるじゃん」とポジティブに捉えていました。もちろん見直すことも大事ですが、プラス思考で前を向くことがもっと大事だと思います。
また、授業の日や自立学習の日にとにかく早く行くことは自信に繋がると思います。早く行ったほうが絶対に勉強時間が多く取れますし、誰よりも早く来て頑張っているという事実は絶対に裏切りません。早くから自立学習に行くことは、自分の自信に直結すると思ってください。やる気は学志舎に行けば、あとから自然と出てきます。絶対合格!!!!応援しています。
親御様
この度、娘が武蔵野北高校に推薦入試で合格することができました。学志舎での学びと経験が大きく実を結ぶ結果となり、親子ともども大変感謝しております。本当にありがとうございました。
学志舎を選んだ理由
学志舎との出会いは、知り合いからとても良い塾があると教えてもらいWebサイトで検索したことがきっかけでした。合格実績、特に推薦入試の驚異的な実績に驚くとともに、布施塾長をはじめとする先生の皆さまの熱心なブログ、たくさんの合格体験記と親御さんメッセージが目に留まりました。「この塾は!?」とものすごく興味がわいたので娘にも見せ、体験に行ってみることになりました。
体験当日、中に入った途端、目の前にはオープンな教室で、塾生の皆さんが誰ひとり声を発することなく小中学生とは思えない集中力で自習をする光景が広がっているではないですか。「この塾はどうなっているんだ!?」またもや驚きでした。村岡先生にご対応いただきテストと面談を受け、指導の方針や受験に対するスタンスをお聞きし、塾はこういうものという印象しかなかった他の大手塾に対し、学志舎は独自性に加え圧倒的な熱量と塾全体の一体感のようなものを感じ、安心して任せられると確信しました。娘も同様な印象を持っていたため、学志舎で高校入試に向かっていくことを自然な流れで決めることができました。
親のチカラupセミナーに参加して
我々親世代が中学生の頃とは学校での教育指針や内容、評価方法など大きく変わっていますし、東京都の高校受験の仕組みと併せて親としても一から勉強という状態ではありましたが、春に参加した親のチカラupセミナーでは、基本的な受験の心得はもちろんのこと、学志舎流の解釈やポイントなど大変わかりやすくご説明いただき、内容の濃さに感心してうなずくばかりでした。
秋のセミナーはこれまでの実績に基づくデータ分析資料が用意され、志望校選びのポイントの解説をいただけたことや、推薦入試のこと、さらには高校・大学に入学後、就活のアドバイスまで、高校受験のための塾の域を超えた、その先の人生のビジョンがあっての今なんだと感じさせてくれる内容にまた感心してうなずくばかりでした。
受験を終えた今、親としての振る舞いを振り返ってみると、もちろん、すべてを理想の形で実践できたかというと中々そうもいきませんでしたが、何かわからなくなったときはいつもセミナー資料を見返してバイブルのように活用させていただきました。
子どもの成長を実感
学志舎に通ってからの大きな変化は、まず、メリハリ、スイッチのオン・オフができるようになったことです。
成績以前に勉強に臨む姿勢が確立できたことは大きな成果だと思います。家で勉強となるとどうしてもだらだらとしてしまい集中できないことがあるという印象でした。学志舎で皆が集中して勉強する姿に感化されたことが大きいとは思いますが、テスト前期間や土日の学志舎での自立学習をフルに活用して、勉強のペースをうまくつかんで取り組めるようになりました。家ではスマホを眺めていたりしていても、オフモードに切り替えているんだなと安心して見守っていられたのは学志舎の教えのおかげです。
一方で、受験を終えた今、高校に入ったらこの子はどこで勉強すればよいのだろうかと心配になってしまうほどです。また、反抗期にもあたる年頃ですので、生活態度などで気になることがあり注意しても素直に受け入れられないことがありますが、挨拶やマナー、取り組む姿勢といった部分も熱心にご指導いただけたおかげで、人としての基礎から大きく成長したと感じており、これは内申upにもつながったものと考えております。
成績については毎月のVもぎの結果で偏差値が毎回1ずつ上がって順調だと思っていたら振り出しに戻るといった波はありましたが、遠目で見れば少しずつ地道に伸ばし志望校に向かって良い結果を出すことができていましたので、自分なりの回復法も取り入れながら乗りきり、受験を通じてメンタル面も強くなったのではないかと考えております。
推薦特訓から合格まで
学志舎名物ともいえる推薦特訓は受験前日まで毎日と、本人はもちろん先生方や卒塾された先輩たちにも支えられ、通常の塾では考えられない一体感の中で力と自信をつけていただいたのだと思います。親の立場としても、一般入試の対策を止めてということに不安がなかったわけではないですが、ブログでは日々詳細に様子を伝えていただいておりましたので、あとは親としてできること、見守る、信じる、メンタルサポート、体調管理に徹することができたと考えています。
推薦入試も無事に終え、進路が決まるその瞬間まで落ち着かないものでしたが、合格発表当日に「合格おめでとうございます」の文字を見て、まず安堵した後に大きな喜びを親子でかみしめることができました。
最後に
中学2年の夏から本当にお世話になりました。学志舎はただの学習塾ではありません。本人の頑張りは必須ですが、そのポテンシャルを最大限に引き出し、親・卒塾生の先輩方のサポートも最大化して受験を通して「人として育ててくれる場」だと思います。我が子の人としての大きな成長はこのような素晴らしい環境の学志舎で過ごした日々によるものと実感しており、高校入学後やその先の人生においてもこの経験が生きてくることを確信しております。本当にありがとうございました。