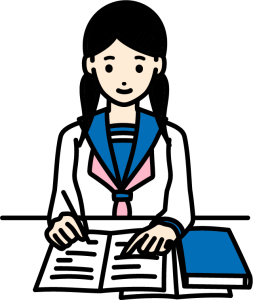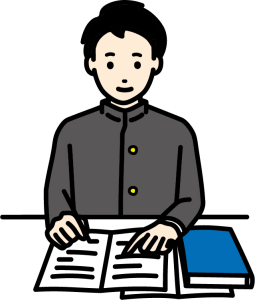合格体験記&親御様メッセージ(2025年 都立西高校:Sくん)※推薦合格
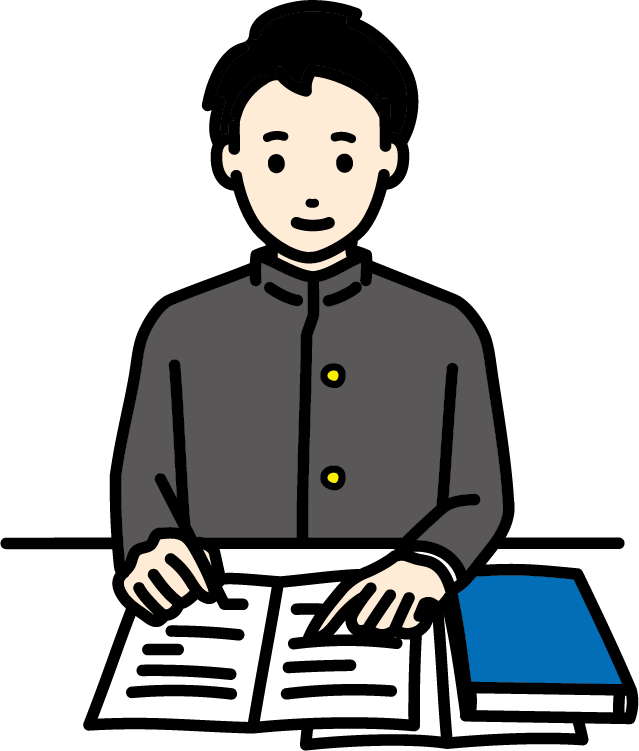
Sくん
入塾のきっかけ
小6の3月頃に、母が連れて行ってくれた塾が学志舎でした。当時私は、都立中入試にて不合格となり、落ち込んでいました。しかし、入塾テスト後に塾長と村岡先生から「高校受験でリベンジだ!」と言われ、気持ちが軽くなったことを覚えています。
また、私は中学3年生の夏までは、部活も含めて学校生活を充実させたいと考えていました。その中で通塾となると、学校生活の妨げや負担にならないか不安でした。しかし、「週2回の授業」というカリキュラムを聞き、非常に驚くと同時に、学志舎なら中学とも両立できるかもしれないと感じたことを覚えています。
入塾前と入塾後の変化
元々集中力や学力には自信がありましたが、「演習量」が不足していました。また、集中力を今のように何時間も持たせることはできませんでした。
入塾してからは、学志舎はこれ以上ない最適な学習環境だと気づきました。周りから聞こえるのはひたすらペンを動かし続ける音だけ、という非常に静かで落ち着いた環境のおかげで、「高い集中力」を身につけることができました。
また、学志舎には一心不乱に問題を解き続ける、ある種異様な光景があります。このお陰で、疲れた時でも「負けていられるか!」と対抗心を燃やし、問題に向き合い続けることができました。
また、中1の1学期の素内申は38でしたが、中3では1学期からオール5の評価を頂くことができました。これは、学志舎がテスト期間は授業をストップし、自習時間に充ててくださったからだと感じています。他にも、先輩方や先生方から教わる内申up法を実践したこともオール5に繋がった要因だと思います。特に、中3の1学期からオール5を掴み取れたことは、精神的に大きな支えとなりました。
落ち込んだ時とその回復法
夏期講習ごろ、私は数学の授業が苦痛でした。関数や図形問題で、どこから手をつければ解くことができるのかわからない私と対照的に、周囲から聞こえる「終わりました」はとても悔しく、焦りを覚えました。
しかし、塾長に相談した際、「今は解けなくて当たり前や。入試問題を今解けないのは周りも同じや。」と言われました。それ以来、ひたすら手を動かし続け、何度も反復して解いていくうちに、不思議と解くことができるようになっていました。
悩む暇があれば手を動かすこと、これが私の中で一番良い解決策だと思います。この解決策は、後の推薦特訓でも活かすことができました。
推薦特訓
作文を少しでも多く書き、頭の中では常に面接のことを考え、疑問があればすぐ先生方や先輩方に質問するようにしていました。1日に作文を9つ書いた日もあり、膨大な演習量を解く中で、自分が短期間に急成長を遂げていることを強く感じたあの感覚は、今までで初めてでした。
他塾ではあり得ない、志望校に合格した卒塾生の先輩方が、私たちを全力でバックアップしてくださる環境は本当にありがたかったです。実際に聞かれた質問を使って面接練習をしたりと、本番を見据えた効果的な練習ができました。
不安になることもありましたが、「悩む暇があれば動け」を常に掲げて行動していました。その結果、自分の能力や内容をよりハイレベルなものに突き詰めることができ、「合格しか見えない」というメンタルに持っていくことができました。
忘れられない言葉
塾長が何度も仰っていた「人と違う結果が欲しいなら、人と違うことをするしかない」という言葉です。中3の1学期からオール5を掴み取れたのは、これを実践したからです。
私は委員会や係活動を「先生と交流する場」と捉えるようにしていました。学級委員を務めることで、先生方とのコミュニケーションをとると同時に、クラスをまとめる存在として先生方から信頼を勝ち取ることができたと思っています。係活動では、成績を上げたい教科の係につくことで、担当の先生と会話する機会を作り出し、同じように信頼を勝ち取りました。これによって授業や提出物以外のところで自己を高めることができました。
勉強以外に教わったこと
「コミュニケーション能力」です。中3初期に村岡先生がしてくださった「コミュニケーション講座」では、「話す」と「聞く」の両方を高めることができたと思います。「相手の目を見る、頷く、相槌を打つ、笑顔」どれも当たり前のことですが、改めて重要性に気づくことができました。この経験もやはり、オール5、そして推薦特訓に生きてきた経験です。
後輩に一言アドバイス
「使えるものは全て使う」この姿勢を持って過ごしてほしいです。例えば、先ほども挙げたように委員会や係活動です。ほかにも先輩にも助けを求めることもありだと思います。内申を取るためにどんなことに取り組んでいたのか聞いたり、高校について質問したりなど、色々なところでアドバイスを受けることは、自分の成長にとても効果的です。仲のいい先輩に相談してみてください。
親御様
学志舎を選んだ理由
3年前、入塾テスト受験と塾長との面談をしたことがつい最近のことのように思い出されます。大手の塾に通い、模試の成績も良く、自信を持って受けた都立中高一貫校は不合格でした。今までのやり方では高校受験を乗りきれないかもしれないと、不安を抱えていた時に見つけた塾が学志舎でした。
「受験に特化した学習カリキュラムがあること」「出題傾向や難易度の情報を得られること」が、それまでの私が考える塾へ通う理由でした。しかし、受け身の姿勢では本当の学力はつかず、今後の人生において本人のためにならないのではないかと思うようになりました。自分で将来のことを真剣に考え、志望校を見つけ、それに向かって主体的に努力する経験をさせたい、そのための環境(塾)を与えたいと思いました。
受験期における子どもの成長
他の塾生の努力する姿に、息子は間違いなく刺激を受けたと思います。私が言わなくても、息子が自立学習に行く日や時間が増えていきました。息子は長時間集中し、塾が閉まるぎりぎりの時間まで勉強をして帰って来ました。時には苦手を分析し、模索しながら懸命に取り組む姿は、私が理想としていた主体的に努力する姿勢そのものでした。学校の勉強にも部活にも塾にも全力投球でした。その結果、3年生からは内申もこれ以上ないほどまで上がり、夏以降は模試の成績も安定して高得点を維持できるようになったことで、私は息子に本当に実力がついたことを確信しました。
また、これは想定外なことでしたが、塾の先生や卒業生の方々との距離がとても近く、塾側と本人との間に深い信頼関係が築けたことも良い結果につながったと思います。志望校選びに迷ったとき、成績が思うように上がらなかったとき、多くの場面で息子にアドバイスや声掛けをしていただきました。息子にとって、とても信頼している塾長や先生方からの声だからこそ、本人はそれを信じて突き進めたのだと思います。
親として心がけたこと
時には親として口出ししたくなることもありました。塾からのアドバイスで第三者からの助言として伝えたり、細かいことはぐっと堪えたり、親の忍耐を試される場面もあったと思います。「親のチカラupセミナー」の受験期の子供の対応についての話は、とてもためになりました。息子の様子の変化も、親にとっては「想定内」と思える心の余裕が生まれました。今思い返してみると体調管理以外でそれほど気を揉むことはなく、穏やかな受験生活を送れたと思います。
最後に
西高推薦入試合格は、息子自身が努力したからこそ勝ち取れた結果です。しかしながら、努力とは簡単なことではなく、気力も体力も必要です。息子が思う存分努力できる環境を与えてくださった学志舎の先生方、同じ志の塾生のみなさんが居たからこそ成せたことだと思います。
これからの息子の長い人生において、この3年間は本当に貴重な経験になりました。努力とは、努力の仕方とは、努力したからこそ見える景色とは。本人がこの先壁に突き当たることがあったとしても、学志舎でやり遂げた経験と自信が助けになってくれると思います。
ありがとうございました。