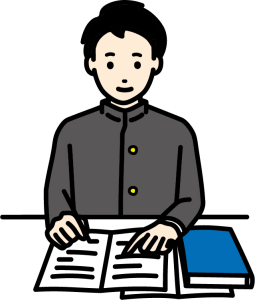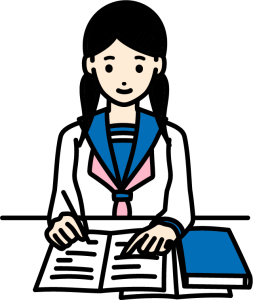合格体験記&親御様メッセージ(2025年 都立武蔵中:Hさん)
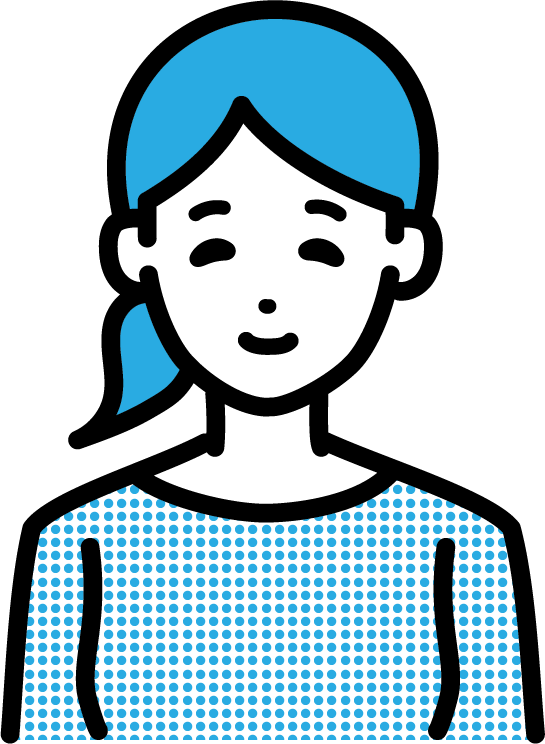
Hさん
入塾のきっかけ
私は小4の9月に学志舎に入塾しました。親の勧めで体験に行った際、人がいないのではないかと思うほどの教室の静けさにとても驚いたことを今でも覚えています。
自立学習をしている一人一人が自分の課題を見つけて、当たり前のように勉強している様子に圧倒され、自分も同じような環境で勉強したいと考え、入塾を決めました。
入塾してわかった勉強の仕方
私は、学志舎に入塾したことで自分に合った勉強の仕方がわかるようになりました。
入塾前までは、学校などで出された宿題のみを行う、という自分では考えようとしない勉強でした。
しかし、自立学習の時間をきちんと確保する学志舎に入塾したことで、自分の課題、その課題を解決するために何を勉強すべきかを考える時間が増え、自分なりの学習方法について理解することができました。この時間があったことは、夏以降、受験勉強が本格化していく中でとても重要であったと感じています。
適性検査では、問われていることにきちんと正対しているか、自分の考えをどう表現するかという部分が問われます。そのものの本質について理解しようとする姿勢、問いを作問者の視点から深く理解しようとする姿勢が重要になってくるのです。学志舎ではそのような物事の本質を一問一問理解していくために先生方が解説をしてくださいます。本質を理解した上でそれをどう本番に活かすかという視点を持ち続けてひたすら演習に取り組む勉強の仕方は、学志舎で得られた一生モノの勉強方法だと思います。
先生の言葉
授業の中で何度も聞いた「学力は質×量によって向上する」という言葉は受験生活の中で最も印象に残り、最も大切にしていた言葉だったと思います。
質×量のうち「量」については過去問演習をひたすら行うことだと思います。私自身、適性Ⅰはすべての作文で「合格!」という字をもらうまで、適性Ⅱ、Ⅲは分からない問題がなくなるまですべての過去問を5周以上は演習しました。
では、「質」はどのようにして高めていけばよいのか、初めのうちは理解できていませんでした。「質」について理解できるようになってきたのは夏ごろからだったと思います。自立学習に通うことが生活の一部となり、有効な時間の使い方が分かってきました。
私が質を高めるために行ったことは、過去問や模試の分析です。自分の間違えた部分から次の模試などへの課題を見つけるとともに、良かった部分、前回よりも成長できた部分を紙に書き、客観的に理解しようと心掛けました。この分析により本番でもいつも通り問題を解けるようにする対応力を体に染み込ませることができました。問題文のチェックや情報の整理、表や図形に書き込むなどの習慣もいつの間にか身に付いていました。
このように「質と量のバランス」が分かるようになってからは、今の自分に足りていないのは過去問演習なのか分析なのかをすぐに判断できるようになり、模試の結果が悪く落ち込んでいるときでも次に活かせれば良い!と切り替えることができました。質×量が1×1からスタートした受験勉強が最後には100×100になっていたと自信を持って言うことができるようになりました。
人によって「質」や「量」を補う方法は違うと思います。だからこそ時間がある時は学志舎に行き、そのバランスについて考えることが重要なのだと思います。
受験期に大切にしたこと
受験期、私が一番大切にしたことは適度な休憩です。受験期はどうしても焦ってしまうと思うし、周りと比べてしまうと思います。だからといって、休憩なしに勉強を続けてしまうとかえって効率が悪くなってしまうのではないでしょうか。
私は、受験日の前日の自立学習でも、お昼ご飯は友達と外に行ってお話をしながら食べていました。休憩をすることにより、切り替えることができると思います。勉強が辛いと思う前に休憩をとることが大事です。過去問演習に疲れたと思ったら簡単な計算問題や理科の問題を10分ほどでも解くことをおすすめします!
勉強面以外で教わったこと
学志舎では勉強以外に「当たり前のことを当たり前に行う」ということを教わりました。
教室に入るときは挨拶をする。先生方と話すときは敬語で。ゴミはきちんと捨てる。机椅子をそろえる。忘れ物はしない。など、これらすべて当たり前のことですが、実行するのは難しいことです。学志舎ではこれらのことを当たり前に行うという習慣を身に付けることができました。
後輩のみなさんへ
受験が近づいてくると不安や緊張の気持ちがとても大きくなってくると思います。しかし、大丈夫です!私たちは「始め!」と言われると自動的に手が動き、頭がフル回転するようになっています。授業の時にひたすら同じ空気を味わってきたはずです!
私は、受験当日、検査が終わる最後の1秒まで「まだ点数とれる!」と必死になっていました。今までの努力を自信にして最後の最後まであきらめないでください!
応援しています。
親御様
学志舎を選んだ理由
受験を意識して塾を検討し始めたのは娘が小4の夏、大手塾の夏期講習への参加からでした。そこでは春からのカリキュラムがすでにかなり進んでおり、夏期講習はその復習、総まとめといった内容だったため、娘はついていくのが大変ですぐに音を上げ、塾というものに対して悪印象を抱いてしまいました。
そのような折、学志舎でその年、小4生クラスを9月から開講すると聞き、ここならみんなと一緒にスタートがきれる、と喜んで開講と同時の入塾を決めました。入塾してもしばらくは学校の一歩先を行く程度で大きな負担にならなかったことも良かったと思っています。
受験期&親のチカラupセミナー
入塾は早かったものの、学校でのお友達は受験しない子がほとんどだったためか、なかなか受験モードに入ることができませんでした。塾での様子も娘を通して知るのみで、日々の小テストや学力テストで好成績を取ることがモチベーションにはなっているものの、なかなか中学受験をして志望校に合格するぞ、という気概が湧くまでには至りませんでした。6年生になると、学校の私立受験組がいかにたくさん勉強しているか、志望校は〇〇らしい、などの話が聞こえてきて、都立のみに絞っていて大丈夫だったのか、絶対に受かりたい!なんて気分に、いつなるのだろうかと心配になっていました。
ところが、5月に参加した親のチカラupセミナーで不安が一気に解消されました。短時間のセミナーでしたが気になっていたことがすべて網羅されており、参加前に考えていた数々の質問事項への回答が得られ、満たされた気分で帰宅したことを覚えています。
中でも記憶に残っているのが「子どものやる気スイッチが入らないのですがどうすればいいですか」という想定質問に対し、「自立学習に来てください。中3生に混じって勉強すると自然とやる気になるものです」という村岡先生のご回答。その時には、他の人たちと話すわけでもなく個別に勉強しているだけでやる気になるものなのだろうか?と半信半疑でしたが以下に述べますように夏頃からは自立学習の効果を身に染みて実感することになりました。
セミナーには短時間に必要十分な内容が盛り込まれていました。タイマーを使って休憩時間を測り、開始時刻も終了時刻もぴったり予定どおり。普段の授業もこのように、無駄なく必要にして十分な内容なのだろうな、と想像できました。他の塾は授業時間が長く、日数も多いけれど娘は大丈夫なのだろうか?という不安もこれで解消されました。
夏以降の成長ぶり
夏期講習の頃から自立学習が生活の一部になりました。学校も同じお友達と共に、自立学習+夏期講習に通う毎日です。周囲で同じように勉強している中3生や小6生と競うようにして、最大時間、学志舎に行くことを誇らしく思っているようでした。
秋以降の週末、冬期講習時期、直前期も自立学習には足繁く通い、「第二の家だから」と言うほどに入り浸っていました。
親の関わり
学習面で親が娘に指導する必要は皆無と言っていいほどありませんでした。強いて言うならば、外部模試を受けた後の解説や採点基準に疑問が残ったときに学志舎の先生に確認するように促したぐらいです。学習全般、学志舎の先生方にすべてを頼るようにしました。
外部模試や前受け校の問題についても、分からないことがあれば何であれ学志舎の先生にご相談し、一貫したルールに基づいて問題演習に取り組むようにしました。適Ⅰの作文は100枚以上提出し、いずれも即時添削いただきました。適ⅡやⅢの問題文の問い方に関する疑問、条件の拾い方など細かいことについても、気がかりな点はすぐに先生方に質問し、解決策を提示して頂けたため、娘も迷うことがありませんでした。
最後に
娘が都立武蔵中に合格できたのはひとえに学志舎との出会いのおかげだと思っています。娘本人は本当によく頑張ったと思いますが、決して無理をした感じがしないのです。習い事も最後の2週間ほどお休みしただけでしたし、必要にして十分な受験生活を送ることができたように思います。模試や授業で適性検査型問題を解くことをとても楽しんでおり、受験生活そのものを満喫していました。
親に言われずとも自分で考え、自分で計画を立て、自分で取り組むことができたのは学志舎スピリッツのおかげです。まさに「自立」して学習する習慣が身に付きました。今後の中高生活でも活かせる、仲間と互いに高め合う力、忍耐力、思考力を培える環境を提供頂いたことに深く感謝いたします。ありがとうございました。